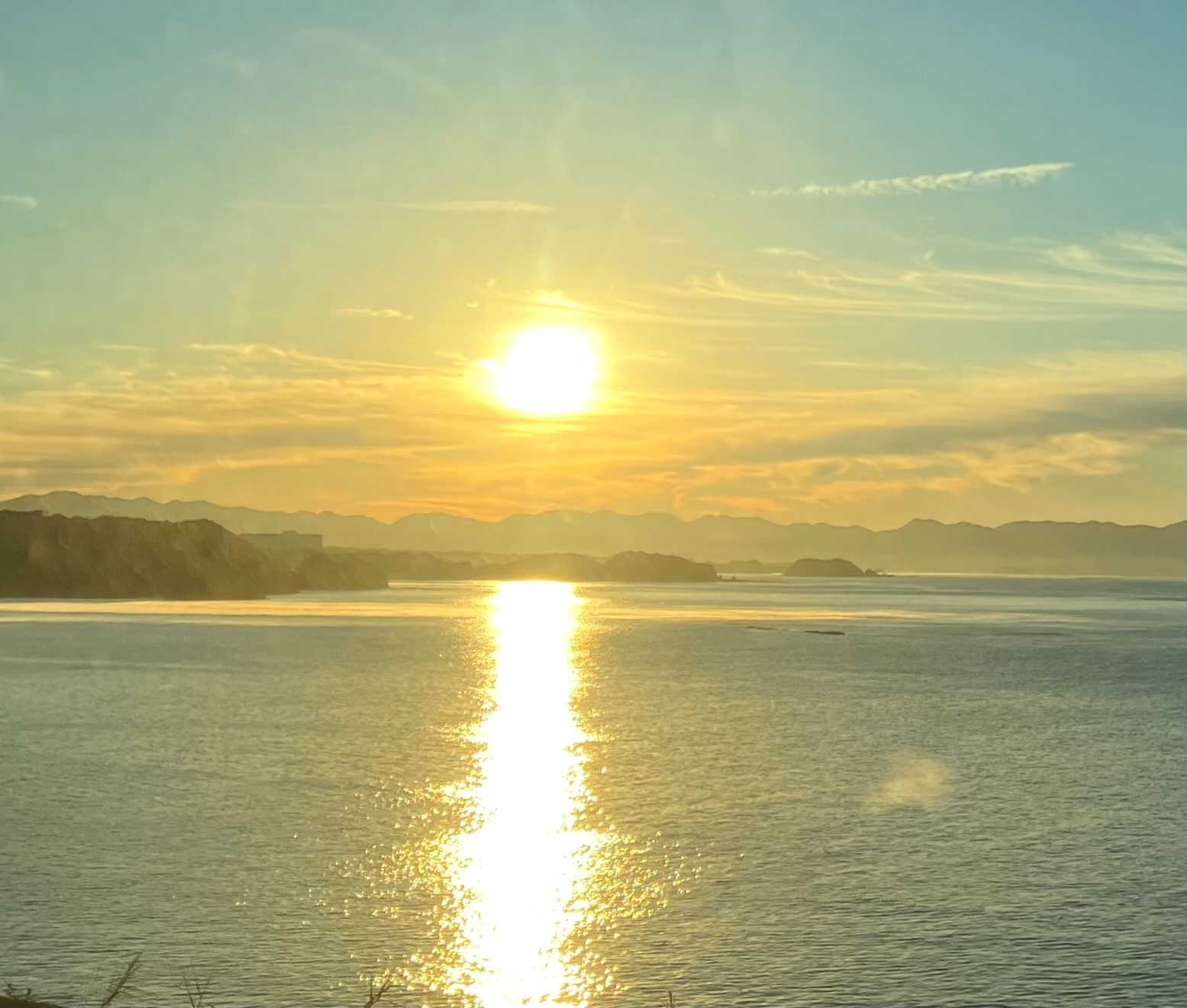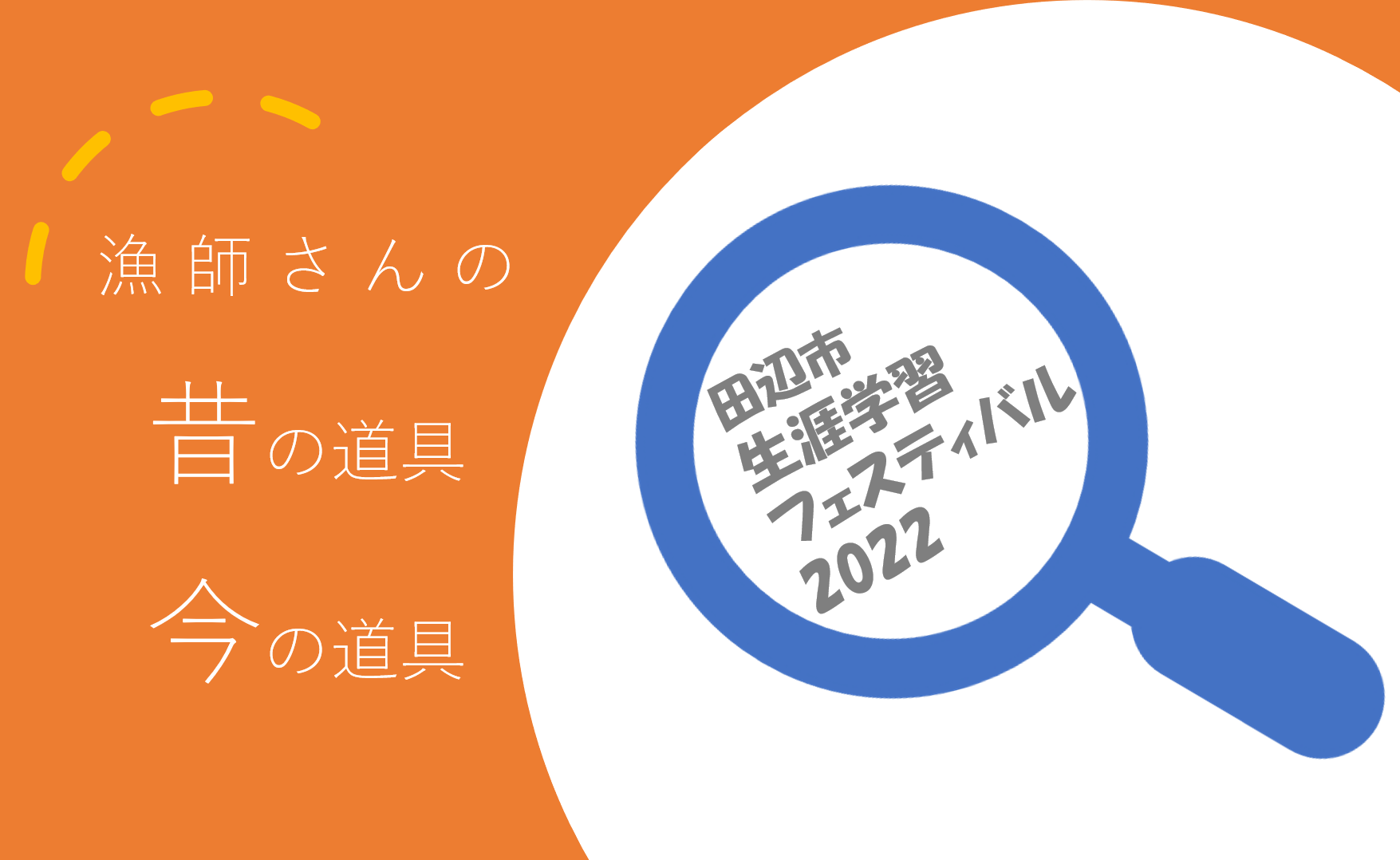アクティブ・レンジャー日記 [近畿地区]:吉野熊野国立公園 田辺
近畿地方環境事務所のアクティブ・レンジャーが、活動の様子をお伝えします。アクティブ・レンジャーとは、自然保護官の補佐役として、国立公園等のパトロール、調査、利用者指導、自然解説などの業務を担う環境省の職員です。管内には、吉野熊野、山陰海岸、瀬戸内海国立公園があります。
2025年07月24日
2025年05月22日

5月 新緑の奇絶峡
田辺
2025年03月31日

ジオパークフェスタへ参加
田辺
2025年01月21日

春の七草を探して
田辺
2025年01月08日
2024年12月27日
2024年12月23日
2024年11月20日
2024年11月15日
2024年09月10日
2024年06月28日
2024年03月28日
2024年02月02日
2024年01月10日
2023年06月20日
2023年05月31日
2023年04月03日
2023年02月03日
2023年01月11日
2022年12月28日
2022年12月15日
2022年09月28日
2022年09月05日
2022年08月29日
2022年06月21日
2022年06月07日
地域園児のヒラメ放流体験
田辺
2022年05月24日
2022年03月28日
2022年01月21日
2021年11月29日
2021年10月15日
2021年09月29日
2021年07月26日
千畳敷のユビナガコウモリ
田辺
2021年06月18日
梅雨の吉野熊野国立公園
田辺
2021年04月30日
2021年03月30日
2021年01月07日
2020年10月27日
2020年09月16日
2020年08月03日
2018年12月13日
2018年11月06日
2018年07月10日
2017年12月08日
2017年06月02日
2016年08月04日
2016年07月21日
アフリカツメガエル
田辺
2016年06月13日
よしくまの海を楽しもう!
田辺