吉野熊野国立公園 吉野
606件の記事があります。
2012年06月27日いわやいわや(岩や窟)
吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太
みなさんこんにちは!吉野の杉本です。
6月23日に上北山村が主催する「心の道ウオーク」のガイドとして和佐又山に行ってきました。今回の日記は和佐又山の更なる魅力について綴ろうかなと考えております。
「アレッ?杉本くんの前回の日記も和佐又山じゃなかった?」という突っ込みは胸の奥にしまっておいて下さい。
今回と記事のネタが被りそうなことはだいたい予想がついていたので、前回は和佐又山の魅力をオオヤマレンゲだけに絞って執筆させていただきました。
ずいぶんと前置きが長くなってしまいましたが、
今回は窟に絞って執筆を進めていきたいと思います。
窟とはなんぞや?と思った方も多いのではないでしょうか?私も数日前までは窟を読むことすらできませんでした。
Web辞書を引いてみると以下のような意味でした。
【窟】[訓読み]いわや [音読み]クツ
意味:ほらあな。人の集まったかくれが
だそうです。
要は、大きな岩の塊にぽっこりと横穴が空いているモノを言います。
和佐又山周遊コースには下の写真の様な岩が目立ちます。

巨岩(6月23日撮影)
巨岩です。誰がなんと言おうと巨岩です。
写真では十分に伝わりきるか心配ですが、「なにせスケールがでかい!!!!」
もう、エクスクラメーションマーク(!)が4つも付くほど圧巻されてしまいました。
こんな巨岩にぽっかりと横穴が空いたのが窟と言われるモノです。

笙の窟(6月23日撮影)
これは笙の窟(しょうのいわや)。
笙(しょう)というのは、雅楽に使われている管楽器の一つで、窟の岩々が笙の形に似ていることからこう名が付いたそうです。
こういった類いのネーミングセンスって素晴らしいですよね。
例えば、星座にしてもかなりのネーミングセンスが光ってると思います。
想像力が豊かと言いますか、発想力がずば抜けていると言いますか、名前を付けた当時の様子が気になるところです。案外、言った者勝ちみたいな感じだったのかもしれませんが・・・
センスのセの字も持ち合わせていない私には、どこがどう笙なのかサッパリでした。
この笙の窟、世界遺産にも登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」大峯奥駈道の大峯七十五靡(なびき)の六十二番目の霊場でもあり、また、かの菅原道真ともゆかりがある場所なんです。
「紀伊山地の霊場と参詣道」や「靡」の話は長くなりそうなので、またの機会にアクティブレンジャー日記で書きます!!
この他にも指弾窟や鷲ノ窟といった様々な窟がありました。

左:鷲の窟(6日14日撮影)
右:指弾の窟(6月23日撮影)
これらの窟達は写真で見るより実物で見た方が何倍もインパクトがあり、そして幻想的です。
みなさんも是非一度、窟を見に来ませんか?
6月23日に上北山村が主催する「心の道ウオーク」のガイドとして和佐又山に行ってきました。今回の日記は和佐又山の更なる魅力について綴ろうかなと考えております。
「アレッ?杉本くんの前回の日記も和佐又山じゃなかった?」という突っ込みは胸の奥にしまっておいて下さい。
今回と記事のネタが被りそうなことはだいたい予想がついていたので、前回は和佐又山の魅力をオオヤマレンゲだけに絞って執筆させていただきました。
ずいぶんと前置きが長くなってしまいましたが、
今回は窟に絞って執筆を進めていきたいと思います。
窟とはなんぞや?と思った方も多いのではないでしょうか?私も数日前までは窟を読むことすらできませんでした。
Web辞書を引いてみると以下のような意味でした。
【窟】[訓読み]いわや [音読み]クツ
意味:ほらあな。人の集まったかくれが
だそうです。
要は、大きな岩の塊にぽっこりと横穴が空いているモノを言います。
和佐又山周遊コースには下の写真の様な岩が目立ちます。

巨岩(6月23日撮影)
巨岩です。誰がなんと言おうと巨岩です。
写真では十分に伝わりきるか心配ですが、「なにせスケールがでかい!!!!」
もう、エクスクラメーションマーク(!)が4つも付くほど圧巻されてしまいました。
こんな巨岩にぽっかりと横穴が空いたのが窟と言われるモノです。

笙の窟(6月23日撮影)
これは笙の窟(しょうのいわや)。
笙(しょう)というのは、雅楽に使われている管楽器の一つで、窟の岩々が笙の形に似ていることからこう名が付いたそうです。
こういった類いのネーミングセンスって素晴らしいですよね。
例えば、星座にしてもかなりのネーミングセンスが光ってると思います。
想像力が豊かと言いますか、発想力がずば抜けていると言いますか、名前を付けた当時の様子が気になるところです。案外、言った者勝ちみたいな感じだったのかもしれませんが・・・
センスのセの字も持ち合わせていない私には、どこがどう笙なのかサッパリでした。
この笙の窟、世界遺産にも登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」大峯奥駈道の大峯七十五靡(なびき)の六十二番目の霊場でもあり、また、かの菅原道真ともゆかりがある場所なんです。
「紀伊山地の霊場と参詣道」や「靡」の話は長くなりそうなので、またの機会にアクティブレンジャー日記で書きます!!
この他にも指弾窟や鷲ノ窟といった様々な窟がありました。

左:鷲の窟(6日14日撮影)
右:指弾の窟(6月23日撮影)
これらの窟達は写真で見るより実物で見た方が何倍もインパクトがあり、そして幻想的です。
みなさんも是非一度、窟を見に来ませんか?
2012年06月15日こんなことやっていますin大台ヶ原☆ 【イベント】
吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥
みなさん、こんにちは。
本日は吉野から小川がお送りします。
とうとう梅雨に入りましたね。洗濯をするのに困る時季が到来です。
さて、そのような中、雨ニモマケズ風ニモマケズ、先日6月10日には、パークボランティアによる自然観察ハイキングが開催されました!
少しどんよりした曇り空ではありましたが、幸いなことに雨は降らず、霞がかったやや幻想的な雰囲気がただよう林の中を歩くことができました。
記念すべき今年度初となる自然観察ハイキングですが、ありがたいことに多くの参加者が集まり、好評を得ることが出来ました☆
今回はその中身をちらっとご紹介したいと思います。
-2.jpg)
ハイキングの様子 【6月 東大台】
東大台を歩いているとたくさんの木々が目に入ってきますが、中でも代表格といえるのが『トウヒ』と『ウラジロモミ』という針葉樹です。
みなさんはこの2つの樹木の違いをご存じですか?
正直、私は大台ヶ原に来たばかりの頃、全然わかりませんでした。
しかし、このハイキングでは写真のように、パークボランティアが、初めて大台ヶ原に来た人にも分かりやすいよう丁寧に東大台の自然について教えてくれます。
私もパークボランティアのみなさんのおかげで、今は着々と大台ヶ原オタクへの道を歩みつつある、と思っています(笑)。
そして、今の時季(6月)にはこのようなかわいらしい花も咲いております!
071.jpg)
シロヤシオ(ゴヨウツツジ) 【6月東大台】
歩いていると頭上にちらほらと見えてきます。雨の日には、花の中で小さな虫が雨宿りをしているのを見ることができるかもしれません☆
このように大台ヶ原には、針葉樹だけでなく、きれいな花を咲かせる木々、ブナやカエデなどの広葉樹など様々な木々があります。
今後も下記の日程にて、初めて大台ヶ原に来た人でも楽しめる、パークボランティアによる自然観察ハイキングを予定しております。
独自に散策されても味わい深い大台ヶ原ですが、是非この機会に自然観察ハイキングに参加されてみてはいかがでしょう。大台ヶ原の自然をいつもより一歩踏み込んで観ることができ、何割にも増して楽しめるのではないでしょうか。
上記の『トウヒ』と『ウラジロモミ』の違いが知りたいという方も、是非この機会にパークボランティアに聞いてみて下さい☆
日時 :7月22日(日)・10月7日(日) 11:00~15:00
(当日に適したプログラムを行います)
内容 :大台ヶ原で活動するパークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物をご紹介します。
参加費:100円(保険代として)
HP :http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0604a.html
本日は吉野から小川がお送りします。
とうとう梅雨に入りましたね。洗濯をするのに困る時季が到来です。
さて、そのような中、雨ニモマケズ風ニモマケズ、先日6月10日には、パークボランティアによる自然観察ハイキングが開催されました!
少しどんよりした曇り空ではありましたが、幸いなことに雨は降らず、霞がかったやや幻想的な雰囲気がただよう林の中を歩くことができました。
記念すべき今年度初となる自然観察ハイキングですが、ありがたいことに多くの参加者が集まり、好評を得ることが出来ました☆
今回はその中身をちらっとご紹介したいと思います。
-2.jpg)
ハイキングの様子 【6月 東大台】
東大台を歩いているとたくさんの木々が目に入ってきますが、中でも代表格といえるのが『トウヒ』と『ウラジロモミ』という針葉樹です。
みなさんはこの2つの樹木の違いをご存じですか?
正直、私は大台ヶ原に来たばかりの頃、全然わかりませんでした。
しかし、このハイキングでは写真のように、パークボランティアが、初めて大台ヶ原に来た人にも分かりやすいよう丁寧に東大台の自然について教えてくれます。
私もパークボランティアのみなさんのおかげで、今は着々と大台ヶ原オタクへの道を歩みつつある、と思っています(笑)。
そして、今の時季(6月)にはこのようなかわいらしい花も咲いております!
071.jpg)
シロヤシオ(ゴヨウツツジ) 【6月東大台】
歩いていると頭上にちらほらと見えてきます。雨の日には、花の中で小さな虫が雨宿りをしているのを見ることができるかもしれません☆
このように大台ヶ原には、針葉樹だけでなく、きれいな花を咲かせる木々、ブナやカエデなどの広葉樹など様々な木々があります。
今後も下記の日程にて、初めて大台ヶ原に来た人でも楽しめる、パークボランティアによる自然観察ハイキングを予定しております。
独自に散策されても味わい深い大台ヶ原ですが、是非この機会に自然観察ハイキングに参加されてみてはいかがでしょう。大台ヶ原の自然をいつもより一歩踏み込んで観ることができ、何割にも増して楽しめるのではないでしょうか。
上記の『トウヒ』と『ウラジロモミ』の違いが知りたいという方も、是非この機会にパークボランティアに聞いてみて下さい☆
日時 :7月22日(日)・10月7日(日) 11:00~15:00
(当日に適したプログラムを行います)
内容 :大台ヶ原で活動するパークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物をご紹介します。
参加費:100円(保険代として)
HP :http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0604a.html
2012年06月14日オオヤマレンゲ【植物】
吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太
みなさんこんにちは!吉野の杉本です。
6月14日に和佐又山へ巡視に行ってきたのですが、オオヤマレンゲがキレイな花を咲かせていました。

オオヤマレンゲは漢字では「大山蓮華」と書きます。その名の通り【大】きい(高い)【山】に咲く【蓮】のようなカップ状の白い【花】を付ける植物です。
少し下向きに花を付けるなかなか奥ゆかしいヤツです。
まだ蕾のままのモノも多く、見頃はこれからって感じですね。

蕾は蕾でかわいらしいです。

中を覗くと黄色い葯(やく)があり、なかなか良い香りがします。この芳香作用で登山の疲れを癒やしてくれます(※効果には個人差があります)。
よくホームセンターなどで観賞用として売られているオオヤマレンゲっぽい花がありますが、あれは母種のオオバオオヤマレンゲという植物で、中国や朝鮮半島が原産です。
みなさんも是非、オオヤマレンゲを見に来ませんか。
かわいらしい花ですが、種も含め、くれぐれも持ち帰ったりしませんようにお願いいたします。
こういった自然を後世に残し、多くの人が感動できるよう、ご協力お願いいたします。
6月14日に和佐又山へ巡視に行ってきたのですが、オオヤマレンゲがキレイな花を咲かせていました。

オオヤマレンゲは漢字では「大山蓮華」と書きます。その名の通り【大】きい(高い)【山】に咲く【蓮】のようなカップ状の白い【花】を付ける植物です。
少し下向きに花を付けるなかなか奥ゆかしいヤツです。
まだ蕾のままのモノも多く、見頃はこれからって感じですね。

蕾は蕾でかわいらしいです。

中を覗くと黄色い葯(やく)があり、なかなか良い香りがします。この芳香作用で登山の疲れを癒やしてくれます(※効果には個人差があります)。
よくホームセンターなどで観賞用として売られているオオヤマレンゲっぽい花がありますが、あれは母種のオオバオオヤマレンゲという植物で、中国や朝鮮半島が原産です。
みなさんも是非、オオヤマレンゲを見に来ませんか。
かわいらしい花ですが、種も含め、くれぐれも持ち帰ったりしませんようにお願いいたします。
こういった自然を後世に残し、多くの人が感動できるよう、ご協力お願いいたします。
2012年06月08日大台ヶ原の動物たち【動物】
吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥
こんにちは!!
本日は、吉野から大台ヶ原担当の小川がお送りします。
だんだんと暑くなり夏が近づいてきたなと思う今日この頃ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
山を訪れる度に新しい植物や虫を見つけ、様々な鳥のさえずりを聞き、ちょっと歩くだけで新しい発見がいっぱいです。そうそう、エゾハルゼミも鳴き始めました。大台ヶ原はすっかり恋の季節です。
そこで今回は、今の時季にみられる動物をご紹介したいと思います。
まずは、こちら!!

エゾハルゼミ (6月 東大台)
エゾハルゼミの羽化の瞬間です。
斜め前側から撮ったものなので、少し見づらいかもしれませんが、幼虫の殻から成虫が出てきているのがわかるでしょうか。
このアングルではなんだか違う1匹の虫に見えそうです…(苦笑)
大体のセミは暗いときに羽化するのですが、大台ヶ原では、歩いているとその瞬間を目にすることがあります。
歩道脇の木の幹やササをよく見ていると、抜け殻がくっついているのが発見できるかもしれません。
お次はこちら!

ナガレヒキガエル (6月 東大台)
少し眠たそうなお目々が大変愛らしいカエルちゃんです。手の平よりも更に小さいサイズでしたので、子どものようです。
他のヒキガエルが水たまりなど止水の中で産卵するのに対し、彼らは渓流の中で産卵をするという、なかなか珍しい特徴を持っています。水流に近い林や森にいますので、歩道を歩きながら脇のササの中をそっとのぞいて見ると、目が合うかもしれません☆
では、最後にべっぴんさんを紹介しましょう。

カケス (5月 東大台)
大台ヶ原では、たくさんの鳥の声がきけますが、その姿を捉えるのはなかなか難しいものです。そこに、いかにも撮ってくれと言わんばかりに登場してくれた鳥がこの子です。
「ジェー」というしわがれた声が聞こえれば近くにいるかもしれません。運が良ければ、地面に落ちた青いきれいな羽根が見られることもあります。
まだまだ、みなさんに紹介したい生き物がたくさんいますが、続きは次回にて☆
さまざまな動植物にあふれるシーズン真っ盛りの大台ヶ原。
一年を通して雨が多い場所ですが、これからは夏の前に梅雨がやってきますので、訪れる際には雨具をお忘れなきようご注意下さい。
また、東大台では下記の日程にて、パークボランティアによる自然観察ハイキングというイベントを今年も予定しております。
日時 :6月10日(日) ・7月22日(日)・10月7日(日) 11:00~15:00
(当日に適したプログラムを行います)
内容 :大台ヶ原で活動するパークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物をご紹介します。
参加費:100円(保険代として)
HP :http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0604a.html
みなさん、是非ご参加下さい☆
本日は、吉野から大台ヶ原担当の小川がお送りします。
だんだんと暑くなり夏が近づいてきたなと思う今日この頃ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
山を訪れる度に新しい植物や虫を見つけ、様々な鳥のさえずりを聞き、ちょっと歩くだけで新しい発見がいっぱいです。そうそう、エゾハルゼミも鳴き始めました。大台ヶ原はすっかり恋の季節です。
そこで今回は、今の時季にみられる動物をご紹介したいと思います。
まずは、こちら!!

エゾハルゼミ (6月 東大台)
エゾハルゼミの羽化の瞬間です。
斜め前側から撮ったものなので、少し見づらいかもしれませんが、幼虫の殻から成虫が出てきているのがわかるでしょうか。
このアングルではなんだか違う1匹の虫に見えそうです…(苦笑)
大体のセミは暗いときに羽化するのですが、大台ヶ原では、歩いているとその瞬間を目にすることがあります。
歩道脇の木の幹やササをよく見ていると、抜け殻がくっついているのが発見できるかもしれません。
お次はこちら!

ナガレヒキガエル (6月 東大台)
少し眠たそうなお目々が大変愛らしいカエルちゃんです。手の平よりも更に小さいサイズでしたので、子どものようです。
他のヒキガエルが水たまりなど止水の中で産卵するのに対し、彼らは渓流の中で産卵をするという、なかなか珍しい特徴を持っています。水流に近い林や森にいますので、歩道を歩きながら脇のササの中をそっとのぞいて見ると、目が合うかもしれません☆
では、最後にべっぴんさんを紹介しましょう。

カケス (5月 東大台)
大台ヶ原では、たくさんの鳥の声がきけますが、その姿を捉えるのはなかなか難しいものです。そこに、いかにも撮ってくれと言わんばかりに登場してくれた鳥がこの子です。
「ジェー」というしわがれた声が聞こえれば近くにいるかもしれません。運が良ければ、地面に落ちた青いきれいな羽根が見られることもあります。
まだまだ、みなさんに紹介したい生き物がたくさんいますが、続きは次回にて☆
さまざまな動植物にあふれるシーズン真っ盛りの大台ヶ原。
一年を通して雨が多い場所ですが、これからは夏の前に梅雨がやってきますので、訪れる際には雨具をお忘れなきようご注意下さい。
また、東大台では下記の日程にて、パークボランティアによる自然観察ハイキングというイベントを今年も予定しております。
日時 :6月10日(日) ・7月22日(日)・10月7日(日) 11:00~15:00
(当日に適したプログラムを行います)
内容 :大台ヶ原で活動するパークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物をご紹介します。
参加費:100円(保険代として)
HP :http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0604a.html
みなさん、是非ご参加下さい☆
2012年06月04日エコツアーガイドの心得【その他・植物】
吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太
みなさんこんにちは!吉野の杉本です。
上北山村が主催する「心の道ウォーク」というイベントで5月31日に又剱山へ、6月1日に行者還岳へ参加者のツアーガイドとして参加してきました。
今振り返ってみると、うまくガイドとしての務めを果たせたかどうかについては微妙なところなんですが・・・
というのも、わたくし、ガイドのお仕事は今回が初めてなのです。
学生時代に、ため池ではしゃぎ回ったり、シカやサルを追いかけてたり、森林ボランティアに参加したりと様々なフィールドを駆け巡ってましたが、一般の方々を相手にフィールドを歩きながら動植物の説明を行うなんてことは未経験でした。加えてわたくし「植物」の名前や特徴に関して言えば素人に毛が生えた程度の知識しかありません。
「この木何の木?」と聞かれても「カエデの仲間ですかね~?」(←曖昧)となってしまうわけです。
この2日間、他のガイドさん達のお話をよく聞いて勉強させていただきました。
豊富な知識ももちろんですが、それよりも参加者のみなさんの興味を惹くことの方がガイドにとって大切なんだなと思いました。そして、話し方は説明や解説ではなくてお話なんですね。ただただ、あーだこーだしゃべるのではなく、物語を話すかのような口調とロジックが参加者の興味を惹かせるコツなんだと感じました。
ホオノキの説明一つとっても、「ホオノキは落葉高木でモクレン科に属し、葉は日本の木本の中では最大級の大きさを誇り、材は他の材に比べて柔らかい。そんな木です。」と言われたところで、なかなか覚えることはできませんよね。
ところが、「ホオの特徴と言ったらなんといっても葉っぱ。大きくておにぎりとか包めそうですよね。「包」装できる木だからホオノキ。今で言うところのサランラップやアルミホイルみたいな用途として使われていました。また木材としても優秀で、柔らかい板なので、まな板などによく使われていました。」と言われると、「ホオ....」と感嘆の声を上げてしまいます。ホオノキだけにね。
ガイドとしてもアクティブレンジャーとしてもまだまだ未熟な私が、初めてのツアーガイドを通して感じたことでした。
もしみなさんがエコツアーなどに参加された場合、どんなツアーガイドさんがいいですか?
きっと人それぞれ、聞きたい話が違ってくると思うんです。動物の話が聞きたいとか、植物の話が聞きたいとか、逆にこんな話をしたいなどなど、少し考えただけでもたくさん出てきます。
ツアー参加者のツボを押さえることも大切になってきますよね。
写真も何もないままだとなんか寂しいので、道中に見つけたおもしろい植物を紹介します。
その1 朽ちていて分かりにくいのですが、多分ブナの切り株から生えてきたリョウブ(又剱山で撮影)

はじめ萌芽更新(ほうがこうしん:生きている切り株から木が再び成長を始めること)しているのかと思いきや、別の植物が生えていることから、切り株にリョウブの種がついたんでしょうかね。
その2 ゴヨウマキの幹から生えてきたシャクナゲ(又剣山で撮影)

生き物たちの共生っておもしろいです。こちらもシャクナゲの種が飛んできて実生したのでしょうかね。
その3 尾根部に繁茂するバイケイソウ(行者還岳で撮影)

バイケイソウに関してはこちらの記事の後半をご覧ください。
尾根部の地面って降った雨が流れていってしまうのに、てっぺんなので上から水が流れてくることもなく、日がよく当たるため、乾いた地面になりやすいんです。しかし、バイケイソウって湿潤な地面などに繁殖しやすい植物なのでおもしろいなぁーと眺めていました。それだけ大峯山は雨や霧が多い地域ということなのでしょう。
上北山村が主催する「心の道ウォーク」というイベントで5月31日に又剱山へ、6月1日に行者還岳へ参加者のツアーガイドとして参加してきました。
今振り返ってみると、うまくガイドとしての務めを果たせたかどうかについては微妙なところなんですが・・・
というのも、わたくし、ガイドのお仕事は今回が初めてなのです。
学生時代に、ため池ではしゃぎ回ったり、シカやサルを追いかけてたり、森林ボランティアに参加したりと様々なフィールドを駆け巡ってましたが、一般の方々を相手にフィールドを歩きながら動植物の説明を行うなんてことは未経験でした。加えてわたくし「植物」の名前や特徴に関して言えば素人に毛が生えた程度の知識しかありません。
「この木何の木?」と聞かれても「カエデの仲間ですかね~?」(←曖昧)となってしまうわけです。
この2日間、他のガイドさん達のお話をよく聞いて勉強させていただきました。
豊富な知識ももちろんですが、それよりも参加者のみなさんの興味を惹くことの方がガイドにとって大切なんだなと思いました。そして、話し方は説明や解説ではなくてお話なんですね。ただただ、あーだこーだしゃべるのではなく、物語を話すかのような口調とロジックが参加者の興味を惹かせるコツなんだと感じました。
ホオノキの説明一つとっても、「ホオノキは落葉高木でモクレン科に属し、葉は日本の木本の中では最大級の大きさを誇り、材は他の材に比べて柔らかい。そんな木です。」と言われたところで、なかなか覚えることはできませんよね。
ところが、「ホオの特徴と言ったらなんといっても葉っぱ。大きくておにぎりとか包めそうですよね。「包」装できる木だからホオノキ。今で言うところのサランラップやアルミホイルみたいな用途として使われていました。また木材としても優秀で、柔らかい板なので、まな板などによく使われていました。」と言われると、「ホオ....」と感嘆の声を上げてしまいます。ホオノキだけにね。
ガイドとしてもアクティブレンジャーとしてもまだまだ未熟な私が、初めてのツアーガイドを通して感じたことでした。
もしみなさんがエコツアーなどに参加された場合、どんなツアーガイドさんがいいですか?
きっと人それぞれ、聞きたい話が違ってくると思うんです。動物の話が聞きたいとか、植物の話が聞きたいとか、逆にこんな話をしたいなどなど、少し考えただけでもたくさん出てきます。
ツアー参加者のツボを押さえることも大切になってきますよね。
写真も何もないままだとなんか寂しいので、道中に見つけたおもしろい植物を紹介します。
その1 朽ちていて分かりにくいのですが、多分ブナの切り株から生えてきたリョウブ(又剱山で撮影)

はじめ萌芽更新(ほうがこうしん:生きている切り株から木が再び成長を始めること)しているのかと思いきや、別の植物が生えていることから、切り株にリョウブの種がついたんでしょうかね。
その2 ゴヨウマキの幹から生えてきたシャクナゲ(又剣山で撮影)

生き物たちの共生っておもしろいです。こちらもシャクナゲの種が飛んできて実生したのでしょうかね。
その3 尾根部に繁茂するバイケイソウ(行者還岳で撮影)

バイケイソウに関してはこちらの記事の後半をご覧ください。
尾根部の地面って降った雨が流れていってしまうのに、てっぺんなので上から水が流れてくることもなく、日がよく当たるため、乾いた地面になりやすいんです。しかし、バイケイソウって湿潤な地面などに繁殖しやすい植物なのでおもしろいなぁーと眺めていました。それだけ大峯山は雨や霧が多い地域ということなのでしょう。
2012年05月22日チェーンソー講習【その他】
吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太
みなさんこんにちは。
みなさんは21日の金環日食はごらんになられましたか?
タイミングを逃して日食しか見られなかった杉本です。
さてさて、5月17、18日のの二日間にかけて「チェーンソー作業従事者 特別教育」を受けて来ました。
大台ヶ原などにある防鹿柵の維持管理にこれからチェーンソーを使う事が予想されるので、チェーンソーの使い方やメンテナンスの仕方などを勉強してきました。
特に安全かつ健康被害が出ないようチェーンソーを扱うために大切なことを中心に勉強してきました。
そのレクチャーの中に目立てと呼ばれる、チェーンソーの刃の研ぎ方も勉強し、実際にチェーンソーの刃を研いだ後、そのチェーンソーで丸太を切る実習も行いました。
目立ては、切れ味を良好にし、作業時間を短くするだけでなく、体に伝わる振動も軽減できるので、振動障害などのリスクを減らすことができる上に、燃費も良くなるので重要なメンテナンスだと言われました。
そんな目立てを終えて、いざぁ丸太切りです。

チェーンソーのエンジンをかける私。
張り切ってます!!

さぁ、エンジンがかかりました。
なんかおっかなびっくりですね。完全に腰が引けてます。
「え?え?どうしたらいいの?」と保護官に目線を送る私
我ながら情けないです・・・・
しかし、いざ切り始めてみると
ががががが・・・・すとんっ!!

実に簡単に切り落とすことができました。
記憶の中にあるチェーンソーよりも格段に切れ味が高い気がしました。
きっと、目立てをきちんと行ったからなんでしょうね。メンテナンスって大切ですね ー。
これから、安全第一でチェーンソーを活かした業務も取り組んで行こうかと思っています。
防鹿柵の修繕や、歩道の手摺(木製)が壊れたぁ。なんて時は私にお任せください。
みなさんは21日の金環日食はごらんになられましたか?
タイミングを逃して日食しか見られなかった杉本です。
さてさて、5月17、18日のの二日間にかけて「チェーンソー作業従事者 特別教育」を受けて来ました。
大台ヶ原などにある防鹿柵の維持管理にこれからチェーンソーを使う事が予想されるので、チェーンソーの使い方やメンテナンスの仕方などを勉強してきました。
特に安全かつ健康被害が出ないようチェーンソーを扱うために大切なことを中心に勉強してきました。
そのレクチャーの中に目立てと呼ばれる、チェーンソーの刃の研ぎ方も勉強し、実際にチェーンソーの刃を研いだ後、そのチェーンソーで丸太を切る実習も行いました。
目立ては、切れ味を良好にし、作業時間を短くするだけでなく、体に伝わる振動も軽減できるので、振動障害などのリスクを減らすことができる上に、燃費も良くなるので重要なメンテナンスだと言われました。
そんな目立てを終えて、いざぁ丸太切りです。

チェーンソーのエンジンをかける私。
張り切ってます!!

さぁ、エンジンがかかりました。
なんかおっかなびっくりですね。完全に腰が引けてます。
「え?え?どうしたらいいの?」と保護官に目線を送る私
我ながら情けないです・・・・
しかし、いざ切り始めてみると
ががががが・・・・すとんっ!!

実に簡単に切り落とすことができました。
記憶の中にあるチェーンソーよりも格段に切れ味が高い気がしました。
きっと、目立てをきちんと行ったからなんでしょうね。メンテナンスって大切ですね ー。
これから、安全第一でチェーンソーを活かした業務も取り組んで行こうかと思っています。
防鹿柵の修繕や、歩道の手摺(木製)が壊れたぁ。なんて時は私にお任せください。
2012年05月16日春の大台百景No.34~No.36【利用・施設】
吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥
こんにちは!!
本日は、吉野から大台ヶ原担当の小川がお送りします☆
最近は暑くなったと思えば、また肌寒くなったりと服装に困る天気が続いていますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
来週の21日は金環日食ですが、晴れて無事にが観られるといいなぁ~と思う今日この頃です。
さて今回は、前回宣言していたように、小川AR選出の大台百景をご紹介します☆
まずはこちら!!

34.
眠りから覚めた蛇 (4月 東大台)
大台ヶ原イチオシの絶景ポイント、大蛇嵓(だいじゃぐら)。
柵のこちら側から見える突き出た岩山が、まるで大蛇の頭のように見えます。開山ほやほやの時にとったもので、あざやかな新緑に瑞々しさを感じます。
見れば見るほど、長い冬眠から目覚めたばかりの蛇が向こうの山のエモノを狙っている!!
……ように思いませんか?(笑)
次にもうひとつ、春の大台ヶ原がこちら!!

35.
ほっこり春色 (4月 伯母峰園地)
大台ヶ原ドライブウェイ途中にある休憩所から見える景色です。
春の息吹が感じられる様々な色に彩られた山に青い空!
人工では作れない、まさに春の自然が織りなす色合いに、なんだか見ているだけであたたかい気持ちになってきます。
そして、最後にもうひとつ!!

36. 水のとばりとこけの天蓋 (5月 東大台)
東大台の中道にある、水が流れる涼しいスポットです。
まるで何か小さい生き物がいる隠れ家や寝床のように、慎ましやかにありますので、見つけた際はそっとのぞいて見てみて下さい。
さてさて、ハイキングにはうってつけな、段々と暖かくなるこの時期。
大台ヶ原も緑が増え、花の蕾がほころび、鳥がさえずりと、にぎやかになってきました。
しかし、山の天気は気まぐれなもの。
ふもとが暖かくても、山は急に寒くなったりします。そして、ここならではの自然を支える大切な要因ではありますが、大台ヶ原は日本有数の雨が多い場所でもあります。
防寒着と雨具を忘れずに、水分補給には気を付けつつ、大台ヶ原の自然をお楽しみ下さい!!
本日は、吉野から大台ヶ原担当の小川がお送りします☆
最近は暑くなったと思えば、また肌寒くなったりと服装に困る天気が続いていますが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
来週の21日は金環日食ですが、晴れて無事にが観られるといいなぁ~と思う今日この頃です。
さて今回は、前回宣言していたように、小川AR選出の大台百景をご紹介します☆
まずはこちら!!

34.
眠りから覚めた蛇 (4月 東大台)
大台ヶ原イチオシの絶景ポイント、大蛇嵓(だいじゃぐら)。
柵のこちら側から見える突き出た岩山が、まるで大蛇の頭のように見えます。開山ほやほやの時にとったもので、あざやかな新緑に瑞々しさを感じます。
見れば見るほど、長い冬眠から目覚めたばかりの蛇が向こうの山のエモノを狙っている!!
……ように思いませんか?(笑)
次にもうひとつ、春の大台ヶ原がこちら!!

35.
ほっこり春色 (4月 伯母峰園地)
大台ヶ原ドライブウェイ途中にある休憩所から見える景色です。
春の息吹が感じられる様々な色に彩られた山に青い空!
人工では作れない、まさに春の自然が織りなす色合いに、なんだか見ているだけであたたかい気持ちになってきます。
そして、最後にもうひとつ!!

36. 水のとばりとこけの天蓋 (5月 東大台)
東大台の中道にある、水が流れる涼しいスポットです。
まるで何か小さい生き物がいる隠れ家や寝床のように、慎ましやかにありますので、見つけた際はそっとのぞいて見てみて下さい。
さてさて、ハイキングにはうってつけな、段々と暖かくなるこの時期。
大台ヶ原も緑が増え、花の蕾がほころび、鳥がさえずりと、にぎやかになってきました。
しかし、山の天気は気まぐれなもの。
ふもとが暖かくても、山は急に寒くなったりします。そして、ここならではの自然を支える大切な要因ではありますが、大台ヶ原は日本有数の雨が多い場所でもあります。
防寒着と雨具を忘れずに、水分補給には気を付けつつ、大台ヶ原の自然をお楽しみ下さい!!
2012年05月09日シュロの花【植物】
吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太
みなさん、こんにちは!吉野自然保護官事務所(大峯地区担当)の杉本です。
吉野山のサクラもすっかり散ってしまい、今はシャクナゲなどのツツジがキレイな花を咲かせています。
吉野自然保護官事務所の近くにはシュロの木があるのですが、その木にふと目をやるとなんと花が咲いておりました。
シュロとは、たまに耳にするシュロ縄の原料です。幹から出ている毛を編み込んだ物がシュロ縄になります。シュロ縄は他のロープに比べ水の中でも切れにくく、水回りで使われたりしています。また、明治時代まではたわしの原料(現在はヤシの木)としても使われたりしていたそうです。
国立公園の中でもたまーにシュロの木を見かけたりしますが、多くは集落跡などに生えています。おそらくは当時の生活に必要な資源であったため、半栽培されていたのでしょう。
シュロの花とはなんとも珍しいと思い、写真をパチり。

シュロの木(5月8日撮影)
みなさんはこの写真のどこに花があるかわかりますか?

シュロの花(5月8日撮影)
実はこの魚卵みたいなのが、花なんです。吉野の大台担当小川ARは「おいしそう!」と言っていました。
さきほど珍しいと書きましたが、おそらく今までに見たことがあっても花と認識していなくて、ただ見過ごしていただけかもしれません。なので、本当は珍しくともなんともないかもしれませんね。
この花、これ全体で一つの花ではなく、いくつもの花の集合体なんです。一つ一つの花は写真のようにものすごく小さいのです。

小さな花(5月8日)
シュロは雌雄異株で雄花と雌花を同じに木につけず、別々の木につけます。
写真のように枝から無数の花がついていることを花序(かじょ)と言い、写真に写っている物は、雄花なので雄花序となります。
雄花と雌花の見分け方は、枝が見えなくなるほど数が多いと雄花で、雄花に比べて数が少ないと雌花になります。
また、花をよーく見てみると、雄花の場合花の中には雄しべが3本~6本であるのに対して、雌花は雌しべが1本しか無いので、そこでも判断ができると思います。
普段なにげなく見ている動植物も、少し注意深く見てみるとなかなか楽しい発見があるものですね。
吉野山のサクラもすっかり散ってしまい、今はシャクナゲなどのツツジがキレイな花を咲かせています。
吉野自然保護官事務所の近くにはシュロの木があるのですが、その木にふと目をやるとなんと花が咲いておりました。
シュロとは、たまに耳にするシュロ縄の原料です。幹から出ている毛を編み込んだ物がシュロ縄になります。シュロ縄は他のロープに比べ水の中でも切れにくく、水回りで使われたりしています。また、明治時代まではたわしの原料(現在はヤシの木)としても使われたりしていたそうです。
国立公園の中でもたまーにシュロの木を見かけたりしますが、多くは集落跡などに生えています。おそらくは当時の生活に必要な資源であったため、半栽培されていたのでしょう。
シュロの花とはなんとも珍しいと思い、写真をパチり。
シュロの木(5月8日撮影)
みなさんはこの写真のどこに花があるかわかりますか?

シュロの花(5月8日撮影)
実はこの魚卵みたいなのが、花なんです。吉野の大台担当小川ARは「おいしそう!」と言っていました。
さきほど珍しいと書きましたが、おそらく今までに見たことがあっても花と認識していなくて、ただ見過ごしていただけかもしれません。なので、本当は珍しくともなんともないかもしれませんね。
この花、これ全体で一つの花ではなく、いくつもの花の集合体なんです。一つ一つの花は写真のようにものすごく小さいのです。

小さな花(5月8日)
シュロは雌雄異株で雄花と雌花を同じに木につけず、別々の木につけます。
写真のように枝から無数の花がついていることを花序(かじょ)と言い、写真に写っている物は、雄花なので雄花序となります。
雄花と雌花の見分け方は、枝が見えなくなるほど数が多いと雄花で、雄花に比べて数が少ないと雌花になります。
また、花をよーく見てみると、雄花の場合花の中には雄しべが3本~6本であるのに対して、雌花は雌しべが1本しか無いので、そこでも判断ができると思います。
普段なにげなく見ている動植物も、少し注意深く見てみるとなかなか楽しい発見があるものですね。
2012年05月01日待ってましたの大台ヶ原山開き!【その他】
吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥
こんにちは!! 今日は吉野から小川ARがお送りします。
ゴールデンウィークまっただ中ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
天気が良い日は外を歩き回りたいものです。
大台ヶ原も、26日にとうとうドライブウェイが開通いたしました!!
ドライブウェイ(DW)を走っている時から、すてきな山の景色が見えます。特にこの季節は新緑がきれいですね。眺めていると、なんだか若返る気分になります。
さて、そのようななか、28日には上の写真を撮った場所でもあります、DW途中の伯母峰園地にて、大台ヶ原山開きがとりおこなわれました。

大台ヶ原山開き (4月 伯母峰園地)
閉山していた期間のDW通行止めの解除を祝うとともに、訪れる方々の安全を祈願して、山の神様に祈りを捧げる、開山時には欠かせない重要な儀式です。
私も参加させて頂きましたが、なんだか身の引き締まる思いでした。
みなさんも来られる際には、どうぞ山の神様に心の中ででも大丈夫ですので挨拶してみて下さい。きっと、より楽しく、体も軽やかに大台ヶ原を満喫できると思います☆
そして、大台ヶ原の開山シーズンには、もう一つ重要なイベントがあります!!
縁の下の力持ちであるパークボランティア(PV)の活動の一つ、春の清掃・歩道改善活動です。

歩道清掃中のPVの頼もしい後ろ姿 (4月 東大台)

ペンキ塗装中のPVの頼もしい塗り姿 (4月 東大台)
ご存じの方も多いと思いますが、大台ヶ原には、パークボランティアという欠かせない存在の人々がおり、利用されるみなさんが、より快適に安全に大台ヶ原を楽しめるよう、様々な活動をしています。
この日も、雲一つないような晴天の下、元気に歩道を歩いてゴミ拾いや、木道階段のペンキ塗りをして下さいました。
しかし、利用されるみなさんの協力のおかげか、今回はゴミが大変少なかったそうです!
大変ありがたいことです。
そして、何よりも嬉しかったのは、通る利用者のみなさんが明るく挨拶して下さったことですね!
私もおぼつかない手つきながら、PVの方々に混じってペンキを塗り塗りしていましたが、やっぱり挨拶っていいなぁ~としみじみ感じていました。
この日は天気も良かったこともあり、たくさんの登山者の方々が来て下さいました☆
ぽかぽか陽気で、山歩きには絶好のシーズンです!
まだ大台ヶ原には行ったことないや~という方も、この機会に是非来てみて下さい。
コース途中には木々や山々を眺めながら、ゆったり休憩できるスペースもありますので、水分・食事補給をしつつ、じっくり大台ヶ原の醍醐味を味わうことができると思います。
それでは、今回は開山したての大台ヶ原の様子をお伝えしました!
次回こそ、さらなる大台百景の紹介をしたいと思います。そこそこに(!?)期待して、次回の更新を楽しみにお待ち下さい!
ゴールデンウィークまっただ中ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
天気が良い日は外を歩き回りたいものです。
大台ヶ原も、26日にとうとうドライブウェイが開通いたしました!!
ドライブウェイ(DW)を走っている時から、すてきな山の景色が見えます。特にこの季節は新緑がきれいですね。眺めていると、なんだか若返る気分になります。
さて、そのようななか、28日には上の写真を撮った場所でもあります、DW途中の伯母峰園地にて、大台ヶ原山開きがとりおこなわれました。

大台ヶ原山開き (4月 伯母峰園地)
閉山していた期間のDW通行止めの解除を祝うとともに、訪れる方々の安全を祈願して、山の神様に祈りを捧げる、開山時には欠かせない重要な儀式です。
私も参加させて頂きましたが、なんだか身の引き締まる思いでした。
みなさんも来られる際には、どうぞ山の神様に心の中ででも大丈夫ですので挨拶してみて下さい。きっと、より楽しく、体も軽やかに大台ヶ原を満喫できると思います☆
そして、大台ヶ原の開山シーズンには、もう一つ重要なイベントがあります!!
縁の下の力持ちであるパークボランティア(PV)の活動の一つ、春の清掃・歩道改善活動です。

歩道清掃中のPVの頼もしい後ろ姿 (4月 東大台)

ペンキ塗装中のPVの頼もしい塗り姿 (4月 東大台)
ご存じの方も多いと思いますが、大台ヶ原には、パークボランティアという欠かせない存在の人々がおり、利用されるみなさんが、より快適に安全に大台ヶ原を楽しめるよう、様々な活動をしています。
この日も、雲一つないような晴天の下、元気に歩道を歩いてゴミ拾いや、木道階段のペンキ塗りをして下さいました。
しかし、利用されるみなさんの協力のおかげか、今回はゴミが大変少なかったそうです!
大変ありがたいことです。
そして、何よりも嬉しかったのは、通る利用者のみなさんが明るく挨拶して下さったことですね!
私もおぼつかない手つきながら、PVの方々に混じってペンキを塗り塗りしていましたが、やっぱり挨拶っていいなぁ~としみじみ感じていました。
この日は天気も良かったこともあり、たくさんの登山者の方々が来て下さいました☆
ぽかぽか陽気で、山歩きには絶好のシーズンです!
まだ大台ヶ原には行ったことないや~という方も、この機会に是非来てみて下さい。
コース途中には木々や山々を眺めながら、ゆったり休憩できるスペースもありますので、水分・食事補給をしつつ、じっくり大台ヶ原の醍醐味を味わうことができると思います。
それでは、今回は開山したての大台ヶ原の様子をお伝えしました!
次回こそ、さらなる大台百景の紹介をしたいと思います。そこそこに(!?)期待して、次回の更新を楽しみにお待ち下さい!

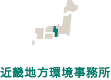
本日は、吉野の大台ヶ原担当、小川がお送りします☆
雨が降ってじっとりと蒸し暑いかと思えば、涼しかったり、お天道様がカンカン照りだったりと天気の気まぐれを感じる今日この頃ですが、みなさんはいかがお過ごしですか?
大台ヶ原も、天気の良い時には雄大な景色を見せてくれたり、雨の日には幽玄な雰囲気を漂わせていたりと日によって様々な顔を見せています。
さて、本日はそんな大台ヶ原で見られる植物たちをご紹介します!
トップバッターは、特徴的なこのお花。
オオミネテンナンショウ【6月 東大台】
思わず中を覗きたくなってしまうような形をしている上に、人目を引くしゃんとした立ち姿。歩道を歩いていると時々見られることがあり、発見したときにはなんだか嬉しくなります。
大台ヶ原には他にもテンナンショウの仲間がいますが、このテンナンショウたち、実はサトイモ科です。これまで私は科名までは知らず、聞いた時には食べられるのかなと思ってしまいました(苦笑)
次は、まるで傘を連想させるこの樹木です。
オオイタヤメイゲツ【6月 東大台】
晴れた日には、少しでもたくさんの光を浴びんと葉を広げるこのカエデですが、雨が降りそうな日にはまるでその準備をするがごとく、葉の傘を作っています。
雨が多い大台ヶ原にぴったりな特徴を持つこの樹木、東大台では上道や中道を歩いていると目にすることが出来ますが、一番のオススメスポットは日出ヶ岳に登る分岐点にあるテラスです。曇りや雨の日で、ちょっと見通しが悪いな~というときには、是非こちらに注目してみて下さい♪
しかし、これら植物は自然の中にいてこそ元気に生き、咲き誇るものです。より多くの方に大台ヶ原を楽しんでもらうためにも、動植物を採ったり持ち帰ったりすることはないよう、目で見て楽しんで下さい☆
このように様々な植物が生息する大台ヶ原では、下記の日程でパークボランティアによる自然観察ハイキングを予定しております。
7月と10月に加え、新たに8月も追加されました!!
夏休みまっただ中での開催ということで、この機会に是非大台ヶ原に来てみてはいかがでしょうか♪
日時 :7月22日(日)・8月12日(日)10月7日(日) 11:00~15:00
(当日に適したプログラムを行います)
内容 :大台ヶ原で活動するパークボランティアが一緒に歩きながら、見どころや季節の動植物をご紹介します。
参加費:100円(保険代として)
HP :http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0604a.html