吉野熊野国立公園 吉野
606件の記事があります。
2010年09月21日大台百景23・24「妖怪と牛石」【その他】
吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子
今回の日記では、「大台百景」と称し、大台ヶ原の魅力を写真を通じてお伝えします。(これまでの大台百景については、ページ右の検索バーに「大台百景」と入力し、GO!をクリック。)
昔から日本にはたくさんの妖怪伝説があるようですが、ここ大台ヶ原も例外ではありません。山上駐車場から歩道を約1時間の所にある「牛石ヶ原」には、今でも大台ヶ原の妖怪が封じ込められているといわれる大きな石「牛石(うしいし)」があります。

23. 東大台の牛石ヶ原「牛石」
よ~く見ると牛が座っているように見えるのだそうです。この石をたたくと、雨が降るのだとか・・・。
(写真提供:大台ヶ原ビジタセンター ふれあいコーディネーター)

24. 濃い霧につつまれた牛石ヶ原
一寸先は霧で何も見えません。うっすらと見える木のシルエットが人間の想像力をかき立て、妖怪伝説が生まれたのでしょうか。
さて、肝心の妖怪ですが、それはそれは恐ろしいものなのだそうです。封じ込められた後でも年に一度、大台ヶ原の厳しい冬の時期に現れるという、そんな妖怪とは・・・?
その正体は、大台ヶ原ビジターセンターの展示室に行くと明らかに!!
---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---
◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山する人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。
◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。
詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!
http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm
昔から日本にはたくさんの妖怪伝説があるようですが、ここ大台ヶ原も例外ではありません。山上駐車場から歩道を約1時間の所にある「牛石ヶ原」には、今でも大台ヶ原の妖怪が封じ込められているといわれる大きな石「牛石(うしいし)」があります。
23. 東大台の牛石ヶ原「牛石」
よ~く見ると牛が座っているように見えるのだそうです。この石をたたくと、雨が降るのだとか・・・。
(写真提供:大台ヶ原ビジタセンター ふれあいコーディネーター)

24. 濃い霧につつまれた牛石ヶ原
一寸先は霧で何も見えません。うっすらと見える木のシルエットが人間の想像力をかき立て、妖怪伝説が生まれたのでしょうか。
さて、肝心の妖怪ですが、それはそれは恐ろしいものなのだそうです。封じ込められた後でも年に一度、大台ヶ原の厳しい冬の時期に現れるという、そんな妖怪とは・・・?
その正体は、大台ヶ原ビジターセンターの展示室に行くと明らかに!!
---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---
◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山する人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。
◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。
詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!
http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm
2010年09月16日ハンター・ナガレヒキガエル【動物】
吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子
大台ヶ原の顔とも言うべき生き物のひとつに、この日記でも何度かご紹介しているヒキガエルの仲間「ナガレヒキガエル」がいます。ふてぶてしい顔つきに、堂々とした態度を見せるこの、愛称「ナガレ」さんには、私の他にも多くのファンがいます。
時は夜の大台ヶ原。普段はなかなか見れないナガレさんの姿を、観察することができました。
電気の灯りに集まる虫たちを狙いに来ていたナガレさん。どんなふうに虫を食べるのか、パークボランティアさんとしばらく観察・・・。
暗がりの中でも、どうやら「視線に入る動くもの」に過敏に反応するようです。
↓画像クリックで拡大

逆に動かないと無反応。頭の上に虫が落ちてきているのに・・・。

虫が動き出すと、じっとその目標を見定め、「構え」の姿勢を取ります。
あまりに速すぎて撮影できませんでしたが、この後、長~い舌をペロッ!と出して虫を口に入れました。
こんなふうにして次々と虫を食べていましたが、なんとここで大変な事が起こりました。近くにいた体長5センチほどの大きなヒゲナガカミキリの動きに、反応したのです。
私とパークボランティアさんは思わず息を呑みました。

予感は的中し、カミキリムシにとびついた!
撮影:大台ヶ原地区パークボランティア 鈴木さん
獲物が大きすぎてひょっとして口が痛い?なんともいえない表情をしています。口の中に入りきらないためか、吐き出しては、食いつき、吐き出してはまた食いつき・・・を繰り返し、結局カミキリムシには逃げられてしまいました。
人間以外の生き物たちの目の見え方の違いには、様々な説があります。ナガレヒキガエルは、動くものと、その距離感を的確に感知しているようでした。その目には、いったいどんな景色が広がっているのか、想像が膨らみます。
時は夜の大台ヶ原。普段はなかなか見れないナガレさんの姿を、観察することができました。
電気の灯りに集まる虫たちを狙いに来ていたナガレさん。どんなふうに虫を食べるのか、パークボランティアさんとしばらく観察・・・。
暗がりの中でも、どうやら「視線に入る動くもの」に過敏に反応するようです。
↓画像クリックで拡大
逆に動かないと無反応。頭の上に虫が落ちてきているのに・・・。
虫が動き出すと、じっとその目標を見定め、「構え」の姿勢を取ります。
あまりに速すぎて撮影できませんでしたが、この後、長~い舌をペロッ!と出して虫を口に入れました。
こんなふうにして次々と虫を食べていましたが、なんとここで大変な事が起こりました。近くにいた体長5センチほどの大きなヒゲナガカミキリの動きに、反応したのです。
私とパークボランティアさんは思わず息を呑みました。

予感は的中し、カミキリムシにとびついた!
撮影:大台ヶ原地区パークボランティア 鈴木さん
獲物が大きすぎてひょっとして口が痛い?なんともいえない表情をしています。口の中に入りきらないためか、吐き出しては、食いつき、吐き出してはまた食いつき・・・を繰り返し、結局カミキリムシには逃げられてしまいました。
人間以外の生き物たちの目の見え方の違いには、様々な説があります。ナガレヒキガエルは、動くものと、その距離感を的確に感知しているようでした。その目には、いったいどんな景色が広がっているのか、想像が膨らみます。
2010年09月14日旅をするチョウPart2 【動物】
吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀
皆さん、こんにちは。
最近随分と気温が下がってきました。吉野では、夜になると肌寒いくらいです。今年は気温の変化が激しいですね。猛暑日が続いたと思ったら、夜は肌寒い・・・このような気温の変化が激しい時に体調を崩しやすいので、体にはお気を付け下さい。
さて今回は、「旅をするチョウ」の第二弾(※)として、「イチモンジセセリ」についてお伝えします。
(※)第一弾は何?と思われた方は、2010年8月30日「旅をするチョウ 【動物】」をご参照下さい!
(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2010/08/30/index.html)
この季節、イタドリやヤブガラシなどの花にたくさんの小さく茶色いチョウが群がっているのを皆さんはご存じでしょうか?この小さいチョウが「イチモンジセセリ」です。このチョウは、セセリチョウというグループに分類されています。パッと見た感じでは、「戦闘機のようなチョウ」、「蛾(ガ)のようなチョウ」です。また、このチョウの幼虫は、イネの葉を丸めて巣を作り、葉を食べてしまうため、「イネツトムシ」とも呼ばれ、農業害虫とされています。もちろんイネだけではなく、エノコログサ(ネコジャラシとも呼ばれます)などのイネ科の植物(一般的な雑草)の葉も食べて成長します。「農業害虫」という悪い印象を受けがちですが、「豊年虫」とも呼ばれ、このチョウが大量に発生する年は米が良く実るとも言われているようです。

写真:ニラ(ユリ科)の花で吸蜜するイチモンジセセリ(セセリチョウ科)

写真:左)イチモンジセセリの幼虫の食べ物、エノコログサ(イネ科) 右)イチモンジセセリの成虫がよく吸蜜するヤブガラシの花(ブドウ科)
このイチモンジセセリも前回のアサギマダラと同じように「旅」をします。「旅」と言っても、アサギマダラのように長距離の旅をするのではなく、晩夏から初秋にかけて山頂から麓へ、北の方から南の方へ小規模な旅をするようです。しかも!「何万匹が集まって集団となり、海を渡って旅をしていた」という報告もあるようです。イチモンジセセリが「なぜ旅をするのか」についてなど、詳しいことはまだ分かっていないようです。
アサギマダラほど多様な環境を利用するわけではありませんが、イチモンジセセリは里山を代表するとても身近なチョウです(今、皆さんの家の花壇にも来ているかも・・・)。アサギマダラの様な優雅さはありませんが、私たちのとても身近なところで生活している一見地味なイチモンジセセリからも、「生物多様性の宝庫」と言われる里山について考えることができます。一人でも多くの人に興味を持って里山について考えてもらえたらと思います。
最近随分と気温が下がってきました。吉野では、夜になると肌寒いくらいです。今年は気温の変化が激しいですね。猛暑日が続いたと思ったら、夜は肌寒い・・・このような気温の変化が激しい時に体調を崩しやすいので、体にはお気を付け下さい。
さて今回は、「旅をするチョウ」の第二弾(※)として、「イチモンジセセリ」についてお伝えします。
(※)第一弾は何?と思われた方は、2010年8月30日「旅をするチョウ 【動物】」をご参照下さい!
(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2010/08/30/index.html)
この季節、イタドリやヤブガラシなどの花にたくさんの小さく茶色いチョウが群がっているのを皆さんはご存じでしょうか?この小さいチョウが「イチモンジセセリ」です。このチョウは、セセリチョウというグループに分類されています。パッと見た感じでは、「戦闘機のようなチョウ」、「蛾(ガ)のようなチョウ」です。また、このチョウの幼虫は、イネの葉を丸めて巣を作り、葉を食べてしまうため、「イネツトムシ」とも呼ばれ、農業害虫とされています。もちろんイネだけではなく、エノコログサ(ネコジャラシとも呼ばれます)などのイネ科の植物(一般的な雑草)の葉も食べて成長します。「農業害虫」という悪い印象を受けがちですが、「豊年虫」とも呼ばれ、このチョウが大量に発生する年は米が良く実るとも言われているようです。
写真:ニラ(ユリ科)の花で吸蜜するイチモンジセセリ(セセリチョウ科)
写真:左)イチモンジセセリの幼虫の食べ物、エノコログサ(イネ科) 右)イチモンジセセリの成虫がよく吸蜜するヤブガラシの花(ブドウ科)
このイチモンジセセリも前回のアサギマダラと同じように「旅」をします。「旅」と言っても、アサギマダラのように長距離の旅をするのではなく、晩夏から初秋にかけて山頂から麓へ、北の方から南の方へ小規模な旅をするようです。しかも!「何万匹が集まって集団となり、海を渡って旅をしていた」という報告もあるようです。イチモンジセセリが「なぜ旅をするのか」についてなど、詳しいことはまだ分かっていないようです。
アサギマダラほど多様な環境を利用するわけではありませんが、イチモンジセセリは里山を代表するとても身近なチョウです(今、皆さんの家の花壇にも来ているかも・・・)。アサギマダラの様な優雅さはありませんが、私たちのとても身近なところで生活している一見地味なイチモンジセセリからも、「生物多様性の宝庫」と言われる里山について考えることができます。一人でも多くの人に興味を持って里山について考えてもらえたらと思います。
2010年09月10日救急講習【その他】
吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子
山で人が倒れてしまった!意識が無い!救急車を呼んでも到着までかなり時間がかかります。どうしよう・・・?そんな時に覚えておきたいのが「応急手当」です。
大台ヶ原地区パークボランティアの活動として、毎年地元の行政組合消防本部の方々のご指導の下「救急講習」を行っています。
呼びかけても意識が無い。まずは周りにいる人達に救急車の要請と、AEDを持ってくるよう指示します。

息が無い、心臓が動いていない。正しい方法で心臓マッサージと人工呼吸を繰り返します。結構な力が必要で、長時間やり続けると息が切れてくるほどです。

AEDによる応急手当。電源を入れると使用方法をすべて説明してくれます。練習中でも緊張してしまう私のような人間にはありがたい機能です。
※AEDは、大台ヶ原ビジターセンターにも設置しています。
毎年の事ながら、1年経つと細かい手順がなかなか思い出せません。定期的に講習を受けることが大事だなと改めて感じました。
大台ヶ原地区パークボランティアの活動として、毎年地元の行政組合消防本部の方々のご指導の下「救急講習」を行っています。
呼びかけても意識が無い。まずは周りにいる人達に救急車の要請と、AEDを持ってくるよう指示します。

息が無い、心臓が動いていない。正しい方法で心臓マッサージと人工呼吸を繰り返します。結構な力が必要で、長時間やり続けると息が切れてくるほどです。

AEDによる応急手当。電源を入れると使用方法をすべて説明してくれます。練習中でも緊張してしまう私のような人間にはありがたい機能です。
※AEDは、大台ヶ原ビジターセンターにも設置しています。
毎年の事ながら、1年経つと細かい手順がなかなか思い出せません。定期的に講習を受けることが大事だなと改めて感じました。
2010年09月09日近畿自然歩道Part2 【利用・施設】【植物】
吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀
皆さん、こんにちは。
9月に入りましたが、吉野ではまだ暑い日々が続いています。夜になれば涼しくなりますが・・・ 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
8月31日に近畿自然歩道の巡視に行ってきました。以前の日記でお伝えした通行止め(※)が通行止め解除になり、その箇所も併せて巡視を行いました。
(※)2010年6月17日 「近畿自然歩道 【その他】【植物】【動物】」をご参照下さい。
(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2010/06/17/index.html)

写真:左)補修後の様子 右)カジカの滝 (ともに8月31日撮影)
歩道が補修され、もと通り、通行可能になりました。補修後の歩道を通り、森の中を歩いて行くと、相変わらず涼しげな(?)カジカの滝が現れます。歩道沿いでは、前回見られなかったツルリンドウ、ハガクレツリフネなどの花が目に付きました。

写真:左)ツルリンドウ(リンドウ科) 右)ハガクレツリフネ(ツリフネソウ科)

写真:左)イヌショウマ(キンポウゲ科) 右)アザミで吸蜜するアカタテハ(タテハチョウ科)
天川村洞川(どろがわ)では随分と涼しくなっており、見られる植物(花)も夏ではなく秋を思わせるものに変わっていました。ひと足早い秋の風情を楽しみに、自然の豊かなところへ出かけてみて下さい。街中では出会えない秋の花々が待っているはずです。
9月に入りましたが、吉野ではまだ暑い日々が続いています。夜になれば涼しくなりますが・・・ 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
8月31日に近畿自然歩道の巡視に行ってきました。以前の日記でお伝えした通行止め(※)が通行止め解除になり、その箇所も併せて巡視を行いました。
(※)2010年6月17日 「近畿自然歩道 【その他】【植物】【動物】」をご参照下さい。
(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2010/06/17/index.html)
写真:左)補修後の様子 右)カジカの滝 (ともに8月31日撮影)
歩道が補修され、もと通り、通行可能になりました。補修後の歩道を通り、森の中を歩いて行くと、相変わらず涼しげな(?)カジカの滝が現れます。歩道沿いでは、前回見られなかったツルリンドウ、ハガクレツリフネなどの花が目に付きました。
写真:左)ツルリンドウ(リンドウ科) 右)ハガクレツリフネ(ツリフネソウ科)
写真:左)イヌショウマ(キンポウゲ科) 右)アザミで吸蜜するアカタテハ(タテハチョウ科)
天川村洞川(どろがわ)では随分と涼しくなっており、見られる植物(花)も夏ではなく秋を思わせるものに変わっていました。ひと足早い秋の風情を楽しみに、自然の豊かなところへ出かけてみて下さい。街中では出会えない秋の花々が待っているはずです。
2010年09月03日ツタウルシ【植物】
吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子
大台ヶ原では、9月に入って秋らしい風が吹くようになりました。植物たちも葉の色を変えはじめ、赤や黄色で賑やかな10月の紅葉のシーズンの準備に入ったようです。
カエデやブナ、ナナカマドなどの紅葉が大台ヶ原でよく見られますが、真っ先に赤くなるツタウルシの紅葉も見逃せません。
※注意※ツタウルシはウルシの仲間です。触ると皮膚がかぶれたり、敏感な方は近づいただけでもかぶれるそうなので、少し離れてご鑑賞ください。

左:8月 青々とした大きな楕円形の葉が3枚グループでつき、枯れ木にぐるぐると巻き付いています。
右:9月 小さい時は葉がギザギザです。小さな葉が可愛らしく紅葉しています。

現在、チラホラと赤や黄色に葉が紅葉し始めているのを見かけます。

10月。紅葉すると真っ赤になります。
昨年の大台ヶ原は、10月の2週目あたりが紅葉のシーズンでした。秋が待ち遠しいですね~。
☆最新の紅葉情報について☆
大台ヶ原ビジターセンター(TEL:0746-83-0312)にお問い合わせください。
カエデやブナ、ナナカマドなどの紅葉が大台ヶ原でよく見られますが、真っ先に赤くなるツタウルシの紅葉も見逃せません。
※注意※ツタウルシはウルシの仲間です。触ると皮膚がかぶれたり、敏感な方は近づいただけでもかぶれるそうなので、少し離れてご鑑賞ください。
左:8月 青々とした大きな楕円形の葉が3枚グループでつき、枯れ木にぐるぐると巻き付いています。
右:9月 小さい時は葉がギザギザです。小さな葉が可愛らしく紅葉しています。

現在、チラホラと赤や黄色に葉が紅葉し始めているのを見かけます。
10月。紅葉すると真っ赤になります。
昨年の大台ヶ原は、10月の2週目あたりが紅葉のシーズンでした。秋が待ち遠しいですね~。
☆最新の紅葉情報について☆
大台ヶ原ビジターセンター(TEL:0746-83-0312)にお問い合わせください。
2010年08月30日旅をするチョウ 【動物】
吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀
皆さん、こんにちは。
暑い日々が続きますが、熱中症などは大丈夫でしょうか。吉野でも、まだまだ暑い日が続きそうです。
突然ですが、皆さんは「旅をするチョウ」というものをご存じでしょうか。「虫が旅をする???」と不思議に思われるのではないでしょうか。この「旅をするチョウ」は、「アサギマダラ」という名前のチョウです。アサギマダラは春に北上し、秋に南下します。どれだけの距離を移動しているかというと、北は信州付近(長野県など)から南は九州付近(沖縄、石垣島など)まで移動しているのです!!何と!中には、本州から台湾まで約1000㎞も移動した個体もいるようです。人間でも1000㎞の移動は大変ですが、このチョウは風に乗って飛ぶことができるのです。

写真:セイタカアワダチソウで吸蜜するアサギマダラ(マダラチョウ科)のオス(2009年10月13日 吉野山にて撮影)
アサギマダラは、翅(はね)のつくりが他のチョウと異なっています。普通、チョウの翅は鱗粉(りんぷん)に覆われており、人間が翅を触ると鱗粉が取れてしまいます。しかしアサギマダラの翅は、触ってもほとんど鱗粉が着かず、他のチョウに比べて翅がしっかりしています。長い旅をするために翅のつくりを変えたのかもしれません。
アサギマダラは、フジバカマやヒヨドリバナなどの白い花が大好きです。秋に山の麓などで白い花に群がる姿を見ることが出来ます。
白い花が多い場所といえば・・・
ウツギなど白い花がたくさん咲いている吉野熊野国立公園の大台ヶ原地区、大峯地区でも見ることが出来ます!ほかにも、ニホンジカの影響で広がってきているバイケイソウの花にもやってくることがあるようです。
.JPG)
写真:シロヤシオの葉上で休むアサギマダラのオス(2009年7月23日 行者還岳にて撮影)
アサギマダラの成虫は白い花を好みますが、幼虫は里山などに生える「キジョラン」や「ガガイモ」などのガガイモ科の植物の葉を食べて成長します(※)。アサギマダラは、まだ解明されていないことが多いチョウですが、山では白い花を見つけて吸蜜し、里山に下りてはガガイモ科の植物に産卵するというように、様々な環境を利用しています。
このように北から南、高山から里山まで、多様な環境を利用している生き物は、どこか一つの環境が失われると命の危機に追いやられることがあります。皆さんもこの優雅に舞うアサギマダラを通じて生き物が棲む環境や生き物同士の繋がりを観察し、生物多様性について考えみてはいかがでしょうか。
(※)昆虫が食べる植物を草では食草、木では食樹と言います。

写真:アサギマダラの食草ガガイモ(ガガイモ科:写真中央の大きい葉)
生物多様性ってなに?と思われた方はこちらへ!!
↓
生物多様性センターホームページ
http://www.biodic.go.jp/
暑い日々が続きますが、熱中症などは大丈夫でしょうか。吉野でも、まだまだ暑い日が続きそうです。
突然ですが、皆さんは「旅をするチョウ」というものをご存じでしょうか。「虫が旅をする???」と不思議に思われるのではないでしょうか。この「旅をするチョウ」は、「アサギマダラ」という名前のチョウです。アサギマダラは春に北上し、秋に南下します。どれだけの距離を移動しているかというと、北は信州付近(長野県など)から南は九州付近(沖縄、石垣島など)まで移動しているのです!!何と!中には、本州から台湾まで約1000㎞も移動した個体もいるようです。人間でも1000㎞の移動は大変ですが、このチョウは風に乗って飛ぶことができるのです。
写真:セイタカアワダチソウで吸蜜するアサギマダラ(マダラチョウ科)のオス(2009年10月13日 吉野山にて撮影)
アサギマダラは、翅(はね)のつくりが他のチョウと異なっています。普通、チョウの翅は鱗粉(りんぷん)に覆われており、人間が翅を触ると鱗粉が取れてしまいます。しかしアサギマダラの翅は、触ってもほとんど鱗粉が着かず、他のチョウに比べて翅がしっかりしています。長い旅をするために翅のつくりを変えたのかもしれません。
アサギマダラは、フジバカマやヒヨドリバナなどの白い花が大好きです。秋に山の麓などで白い花に群がる姿を見ることが出来ます。
白い花が多い場所といえば・・・
ウツギなど白い花がたくさん咲いている吉野熊野国立公園の大台ヶ原地区、大峯地区でも見ることが出来ます!ほかにも、ニホンジカの影響で広がってきているバイケイソウの花にもやってくることがあるようです。
写真:シロヤシオの葉上で休むアサギマダラのオス(2009年7月23日 行者還岳にて撮影)
アサギマダラの成虫は白い花を好みますが、幼虫は里山などに生える「キジョラン」や「ガガイモ」などのガガイモ科の植物の葉を食べて成長します(※)。アサギマダラは、まだ解明されていないことが多いチョウですが、山では白い花を見つけて吸蜜し、里山に下りてはガガイモ科の植物に産卵するというように、様々な環境を利用しています。
このように北から南、高山から里山まで、多様な環境を利用している生き物は、どこか一つの環境が失われると命の危機に追いやられることがあります。皆さんもこの優雅に舞うアサギマダラを通じて生き物が棲む環境や生き物同士の繋がりを観察し、生物多様性について考えみてはいかがでしょうか。
(※)昆虫が食べる植物を草では食草、木では食樹と言います。
写真:アサギマダラの食草ガガイモ(ガガイモ科:写真中央の大きい葉)
生物多様性ってなに?と思われた方はこちらへ!!
↓
生物多様性センターホームページ
http://www.biodic.go.jp/
2010年08月26日大峯百選 其の拾壱 【その他】
吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀
皆さん、こんにちは。
8月ももうすぐ終わりですが、まだまだ暑い日々は続きそうですね。みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、大峯百選 其の拾壱 として、天川村洞川にある「稲村ヶ岳」についてお伝えします。稲村ヶ岳は「女人大峯」とも呼ばれ、多くの人に親しまれている山です(※)。
(※)詳しくは、2010年5月31日 「稲村ヶ岳巡視 【その他】」をご参照下さい。
稲村ヶ岳の見どころは・・・
やはり、山頂からの眺望です。山頂には展望台があり、山上ヶ岳や大普賢岳など周りの山々を見渡すことができます。それでは、稲村ヶ岳山頂展望台から見た四季の変化をご覧下さい。


写真:稲村ヶ岳山頂からの眺望
左上)霧に包まれた山頂(春) 右上)澄み渡った山頂(夏)
左下)紅葉する山々(秋) 右下)雪化粧をした山々(冬)
上の4枚の写真のように、季節、天候などによって様々な顔を見せてくれます。「登山は晴れた日に!」という気持ちもあるかと思いますが、小雨の降る日にはまた違った雰囲気を味わうことが出来ます。雨が降ると霧が出やすく、山頂からの眺望はあまり期待できませんが、道中に見どころがたくさん出てきます。霧に覆われた幻想的な登山道やしっとりと濡れた花々などを見ながら登山を楽しむことができます。

写真:霧でしっとりと濡れたハガクレツリフネ(ツリフネソウ科)
皆さんも様々に変化する「山の顔」を見てみてはいかがでしょうか。晴れの日や雨の日、季節の変化によって行く度に異なる山の顔を見ていると、行く度に新しい発見があるはずです。
8月ももうすぐ終わりですが、まだまだ暑い日々は続きそうですね。みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、大峯百選 其の拾壱 として、天川村洞川にある「稲村ヶ岳」についてお伝えします。稲村ヶ岳は「女人大峯」とも呼ばれ、多くの人に親しまれている山です(※)。
(※)詳しくは、2010年5月31日 「稲村ヶ岳巡視 【その他】」をご参照下さい。
稲村ヶ岳の見どころは・・・
やはり、山頂からの眺望です。山頂には展望台があり、山上ヶ岳や大普賢岳など周りの山々を見渡すことができます。それでは、稲村ヶ岳山頂展望台から見た四季の変化をご覧下さい。
写真:稲村ヶ岳山頂からの眺望
左上)霧に包まれた山頂(春) 右上)澄み渡った山頂(夏)
左下)紅葉する山々(秋) 右下)雪化粧をした山々(冬)
上の4枚の写真のように、季節、天候などによって様々な顔を見せてくれます。「登山は晴れた日に!」という気持ちもあるかと思いますが、小雨の降る日にはまた違った雰囲気を味わうことが出来ます。雨が降ると霧が出やすく、山頂からの眺望はあまり期待できませんが、道中に見どころがたくさん出てきます。霧に覆われた幻想的な登山道やしっとりと濡れた花々などを見ながら登山を楽しむことができます。
写真:霧でしっとりと濡れたハガクレツリフネ(ツリフネソウ科)
皆さんも様々に変化する「山の顔」を見てみてはいかがでしょうか。晴れの日や雨の日、季節の変化によって行く度に異なる山の顔を見ていると、行く度に新しい発見があるはずです。
2010年08月23日アクティブ・レンジャー自然観察会【イベント】
吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子
7月から8月にかけての夏休み期間を中心に5日間、大台ヶ原で吉野自然保護官事務所アクティブ・レンジャー2名による自然観察会を行いました。

↑クリックで拡大!大台ヶ原(東大台)地図と各ツアーのコース。
赤:苔の森でミニエコツアー(約1km) 黄:夏の森でエコハイキング(約2km)
○苔の森でミニエコツアー 時間:1時間30分
平成17年から始まり、吉野自然保護官事務所の歴代アクティブ・レンジャーが継続して行っています。普通に歩けば20分のコースですが、普段見落としがちな自然の不思議を、クイズや紙芝居などを交えながらじっくりお伝えしています。このコースでしか見ることのできない、自然再生の取り組みも紹介しました。

写真:かじられた松ぼっくりのようなものが落ちていました。これは何でしょう?一体誰が食べたのでしょう?
○夏の森でエコハイキング 時間:2時間
新たなコースで、今年初めての試みです。森の緑を感じ、川のせせらぎを聞きながらの自然観察。環境の変化や大台ヶ原で行っている調査を紹介しました。時間配分や、どうすればより自然を体感してもらえるかなど、まだまだ見直すべき点がありますが、今年は、昨年の「苔の森でミニエコツアー」に参加した方がリピーターとして来てくださり、「やってみて良かったな~」と感じました。

写真:大台ヶ原では、毒のある植物が増えてきています。これは何だろう?なぜ増えたのでしょうか?
今年の開催は、残すところあと2日です!※「夏の森でエコハイキング」は終了しました。
■苔の森でミニエコツアー■
☆アクティブ・レンジャーが案内します☆
開催日程:平成22年 9月18日(土)、10月16日(土)
開催時間:午前の部10:40~12:10、午後の部13:30~15:00
問い合わせ:吉野自然保護官事務所(担当:青谷・朝倉)
TEL:0746-34-2202

↑クリックで拡大!大台ヶ原(東大台)地図と各ツアーのコース。
赤:苔の森でミニエコツアー(約1km) 黄:夏の森でエコハイキング(約2km)
○苔の森でミニエコツアー 時間:1時間30分
平成17年から始まり、吉野自然保護官事務所の歴代アクティブ・レンジャーが継続して行っています。普通に歩けば20分のコースですが、普段見落としがちな自然の不思議を、クイズや紙芝居などを交えながらじっくりお伝えしています。このコースでしか見ることのできない、自然再生の取り組みも紹介しました。
写真:かじられた松ぼっくりのようなものが落ちていました。これは何でしょう?一体誰が食べたのでしょう?
○夏の森でエコハイキング 時間:2時間
新たなコースで、今年初めての試みです。森の緑を感じ、川のせせらぎを聞きながらの自然観察。環境の変化や大台ヶ原で行っている調査を紹介しました。時間配分や、どうすればより自然を体感してもらえるかなど、まだまだ見直すべき点がありますが、今年は、昨年の「苔の森でミニエコツアー」に参加した方がリピーターとして来てくださり、「やってみて良かったな~」と感じました。
写真:大台ヶ原では、毒のある植物が増えてきています。これは何だろう?なぜ増えたのでしょうか?
今年の開催は、残すところあと2日です!※「夏の森でエコハイキング」は終了しました。
■苔の森でミニエコツアー■
☆アクティブ・レンジャーが案内します☆
開催日程:平成22年 9月18日(土)、10月16日(土)
開催時間:午前の部10:40~12:10、午後の部13:30~15:00
問い合わせ:吉野自然保護官事務所(担当:青谷・朝倉)
TEL:0746-34-2202

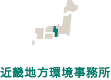
最近吉野では、涼しい日々が続いています。あの暑かった日差しはどこに行ったのか・・・夜になると、布団が恋しくなる!?くらいです。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。
10月9日(土)・10日(日)の2日間、五感で体験しよう!子ども自然体験プロジェクト 大台ヶ原と川上村で学ぶ 『人と自然はこんなにつながっている!』が実施されます。環境省近畿地方環境事務所と奈良県川上村の「森と水の源流館」が行うイベントで、1泊2日で様々な自然体験を満喫できる内容となっています!
写真:五感で学ぼう!子ども自然体験プロジェクトのチラシ
主な内容は・・・
9日
○奈良県川上村の三之公で林業体験や記念品づくり、吉野杉について学びます。
○夜は川上村の旅館(民宿)に宿泊し、奈良といえば(?)のシカ肉をいただきます!食を通じて、生き物の同士の繋がりを考えます。
○晩ご飯の後には、秋が深まった頃に出てくる虫探し!秋にはどんな虫に出会えるでしょうか?
○虫探しの後は、翌日のフィールド 上北山村の大台ヶ原のお話。大台ヶ原とはどういうところ?今、どんな問題が起こっているの?などのお話です。
○そして就寝・・・
10日
○起床後、大台ヶ原へ!車窓から壮大な景色が見られるかも・・・
○到着後、大台ヶ原で問題になっているササとニホンジカの関係を調べます。みんなで大台ヶ原を調べよう!
○昼食をはさんで、本イベントのまとめの新聞づくり。みんなで報告会を行います。
○そして解散・・・
以上のような盛りだくさんの内容が予定されています!
※天候によって内容を変更することがあります。
写真: 大台ヶ原の写真。もしかすると、こんな大台ヶ原が見られるかも!?
参加対象者は小学校4年生~6年生まで、定員は30名(先着順)です。
奈良県川上村と上北山村の豊かな自然の中で、自然環境や生き物について楽しく学ぶことができます。ぜひご参加下さい!皆さんの参加をお待ちしております!!
その他、詳しいことは、森と水の源流館へお問い合わせ下さい。
森と水の源流館
http://www.genryuu.or.jp/