吉野熊野国立公園 熊野
355件の記事があります。
2010年05月07日セイタカシギ 【動物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
先日、那智勝浦町の田んぼで渡り鳥のセイタカシギを確認しました。

セイタカシギ セイタカシギ科
名前の通り、足が長く背が高いシギの仲間です。環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されていて、絶滅の危険が増大している種の一つです。
シギ類の多くは季節によって渡りと呼ばれる移動を行います。この辺りは繁殖地と越冬地を移動する際の中継地になっていて、この時期に観察されます。

上の写真の足に注目してみてください。人の膝の曲がり方とは逆に曲がっていると思いませんか。実はこの曲がっている部分は人のかかとにあたる部分です。つまり真っ直ぐ足を伸ばしている時はつま先立ちの状態というわけです。じっとしている時には、足を真っ直ぐ伸ばしていることが多く、疲れないのかなとちょっと心配してしまいます。
中継地としての利用であるため、多くは1、2日で飛び去ってしまいます。春が過ぎ去っていくのもこんな風にあっという間だと思うと、少し切ない気持ちになります。
セイタカシギ セイタカシギ科
名前の通り、足が長く背が高いシギの仲間です。環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されていて、絶滅の危険が増大している種の一つです。
シギ類の多くは季節によって渡りと呼ばれる移動を行います。この辺りは繁殖地と越冬地を移動する際の中継地になっていて、この時期に観察されます。
上の写真の足に注目してみてください。人の膝の曲がり方とは逆に曲がっていると思いませんか。実はこの曲がっている部分は人のかかとにあたる部分です。つまり真っ直ぐ足を伸ばしている時はつま先立ちの状態というわけです。じっとしている時には、足を真っ直ぐ伸ばしていることが多く、疲れないのかなとちょっと心配してしまいます。
中継地としての利用であるため、多くは1、2日で飛び去ってしまいます。春が過ぎ去っていくのもこんな風にあっという間だと思うと、少し切ない気持ちになります。
2010年04月20日地質の日記念行事参加者募集中 【イベント】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
一昨年前に地質関係の組織や学会により、5月10日が地質の日に制定されました。この度地質の日を記念した自然観察会「地質の日フィールドワーク~太古の自然を感じよう、御浜小石の秘密をさぐれ!~」を企画しています。
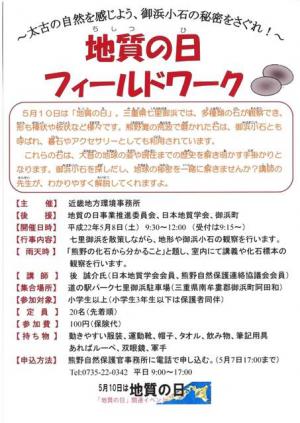
三重県御浜町にある紀伊半島では珍しい直線的な海岸が続く七里御浜にて開催します。
当日は地質学会会員の方を講師としてお招きし、散策しながら、七里御浜の地形や御浜小石と呼ばれる熊野灘から打ち上げられた石等の観察を行います。
熊野川の影響で、棒状、板状や球状などの色々な形をした石ころが観察できます。太平洋の荒波によって削られた御浜小石は、碁石やアクセサリーにも利用されています。
開催場所となっている七里御浜は「日本の自然百選」「日本の白砂青松百選」「21世紀に残したい日本の自然百選」「日本の渚百選」「日本の名松百選」と日本の百選に5つも選ばれていて、風景地としても優れた場所です。

興味や関心のある方は熊野自然保護官事務所まで是非お申し込み下さい。
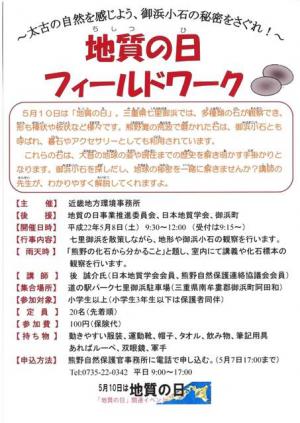
三重県御浜町にある紀伊半島では珍しい直線的な海岸が続く七里御浜にて開催します。
当日は地質学会会員の方を講師としてお招きし、散策しながら、七里御浜の地形や御浜小石と呼ばれる熊野灘から打ち上げられた石等の観察を行います。
熊野川の影響で、棒状、板状や球状などの色々な形をした石ころが観察できます。太平洋の荒波によって削られた御浜小石は、碁石やアクセサリーにも利用されています。
開催場所となっている七里御浜は「日本の自然百選」「日本の白砂青松百選」「21世紀に残したい日本の自然百選」「日本の渚百選」「日本の名松百選」と日本の百選に5つも選ばれていて、風景地としても優れた場所です。
興味や関心のある方は熊野自然保護官事務所まで是非お申し込み下さい。
2010年04月16日新たな季節 【動物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
町中では初々しい新入生の通学姿を目にするようになり、新年度を迎えたことを実感している今日この頃。那智勝浦町にある宇久井ビジターセンターでも、新たな季節の巡りを実感する出来事がありました。
この辺りの海岸付近によく見られる野鳥の1種、イソヒヨドリの巣作りが始まりました!昨年もビジターセンターではイソヒヨドリの営巣が確認されましたので、2年連続となります。

こちらが巣作りを行っているイソヒヨドリの雌です。
少し分かりづらいのですが、巣作りのためにビジターセンターの軒下の隙間に入ったイソヒヨドリです↓

巣材となる草や木の枝などを頻繁に運んでいる姿が確認できます。口でくわえられる分には限りがあるので、何回も行き来していて、とても健気に感じます。
観察する際には、そっと遠くから見守って頂ければと思います。
この辺りの海岸付近によく見られる野鳥の1種、イソヒヨドリの巣作りが始まりました!昨年もビジターセンターではイソヒヨドリの営巣が確認されましたので、2年連続となります。
こちらが巣作りを行っているイソヒヨドリの雌です。
少し分かりづらいのですが、巣作りのためにビジターセンターの軒下の隙間に入ったイソヒヨドリです↓
巣材となる草や木の枝などを頻繁に運んでいる姿が確認できます。口でくわえられる分には限りがあるので、何回も行き来していて、とても健気に感じます。
観察する際には、そっと遠くから見守って頂ければと思います。
2010年04月06日旬情報 【植物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
桜の満開の便りも東北地方まで達したようですが、熊野では花が散り葉桜となった桜もあり、本州最南端の串本町では早生品種の稲作が始まったようで、早くも夏に向けた準備が始まっています。
春が駆け足で過ぎ去ってしまいそうで少し焦燥感にかられますが、熊野管内でもまだ桜を楽しめます。
和歌山県太地町にある平見台園地に植えられている桜が満開を迎えています。

またこの桜の横にある継子投げと呼ばれる場所からの眺望が秀逸です。

継子投げから
継子投げの名前の由来の逸話は以前の日記に投稿しましたので、興味のある方はこちらまで。http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/01/15/index.html
平見台は太平洋が目の前に広がって、南は潮岬の方まで見渡すことができ、非常に開放感に浸れます。桜も見ることができる春爛漫なこの時期の散策はおすすめです。
春が駆け足で過ぎ去ってしまいそうで少し焦燥感にかられますが、熊野管内でもまだ桜を楽しめます。
和歌山県太地町にある平見台園地に植えられている桜が満開を迎えています。
またこの桜の横にある継子投げと呼ばれる場所からの眺望が秀逸です。
継子投げから
継子投げの名前の由来の逸話は以前の日記に投稿しましたので、興味のある方はこちらまで。http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/01/15/index.html
平見台は太平洋が目の前に広がって、南は潮岬の方まで見渡すことができ、非常に開放感に浸れます。桜も見ることができる春爛漫なこの時期の散策はおすすめです。
2010年03月30日海藻帯 【植物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
今年度最後の投稿となる今日は、この時期に海岸で見られる光景について取りあげたいと思います。


宇久井半島松尾からみた海岸
撮影場所は宇久井ビジターセンターの遊歩道に整備された松尾展望広場で、宇久井半島の特徴的な地形である海成段丘※や崖に穴が空いた海蝕洞が確認できます。
※海面近くには、陸地が浸食されたり堆積物が積もったりして平らな土地がつくられます。その後海面下降と土地の隆起があり、上が平坦で端が急な崖の土地が取り残され丘となります。
岩や石の下の部分が帯状に赤褐色に変色していることがわかりますか。
今変色している場所は潮間帯と呼ばれる潮の満ち引きによって海と陸の環境が繰り返される環境にあり、写真では陸上である場所も満潮時には海の中となります。その潮間帯では春の時期は海藻が繁茂し、くっきりとした帯状の線のように見えます。
海岸において近くで見ると、岩に付着しているだけではなく、海中にも海藻が生い茂っていて海の中に森のような茂みが広がっていることが良くわかると思います。
(注意)海藻がついた岩は滑りやすいので、十分注意してください。
宇久井半島松尾からみた海岸
撮影場所は宇久井ビジターセンターの遊歩道に整備された松尾展望広場で、宇久井半島の特徴的な地形である海成段丘※や崖に穴が空いた海蝕洞が確認できます。
※海面近くには、陸地が浸食されたり堆積物が積もったりして平らな土地がつくられます。その後海面下降と土地の隆起があり、上が平坦で端が急な崖の土地が取り残され丘となります。
岩や石の下の部分が帯状に赤褐色に変色していることがわかりますか。
今変色している場所は潮間帯と呼ばれる潮の満ち引きによって海と陸の環境が繰り返される環境にあり、写真では陸上である場所も満潮時には海の中となります。その潮間帯では春の時期は海藻が繁茂し、くっきりとした帯状の線のように見えます。
海岸において近くで見ると、岩に付着しているだけではなく、海中にも海藻が生い茂っていて海の中に森のような茂みが広がっていることが良くわかると思います。
(注意)海藻がついた岩は滑りやすいので、十分注意してください。
2010年03月24日吉野熊野自然観察会 潮岬花を訪ねて 【イベント】【植物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
最近大雨が降ったり、強風が吹いたり、また黄砂の飛来が見られたりと荒れた天候が続きました。そんな中晴天に恵まれた先日の22日に、「吉野熊野国立公園自然観察会 潮岬花を訪ねて」を開催しました。
今回は一般市民の参加者を募り、西日本一帯で実施されているタンポポの分布調査「タンポポ調査・西日本2010」※に合わせて、この時期に花を咲かせるタンポポとその他の海浜植物、すみれや桜等の観察するイベントを本州最南端の潮岬にて開催しました。
※近年在来種(カンサイタンポポ、トウカイタンポポ等)と外来種(セイヨウタンポポ、アカミタンポポ等)の雑種が増え、在来種の減少が見られています。このような自然の変化について市民と一緒に広域的に調べるのが本調査の趣旨であり、環境省も後援しています。
詳細はこちら:http://www.nature.or.jp/Tampopo2010/

潮岬周辺は在来種のトウカイタンポポ(左)と外来種のセイヨウタンポポ(右)が自生しています。前者は夏にかけて他の植物によって日陰となってしまう場所に多く、後者は1年中開けた場所に多くみられます。

観察された様々な花々。春らしい色鮮やかさです。
左上:ウマゴヤシ マメ科、右上:ルリハコベ サクラソウ科、左下:ハマエンドウ マメ科、左下:フデリンドウ リンドウ科
ご紹介した花以外にもオオシマザクラやソメイヨシノの桜や、スミレやオカスミレ等のすみれをはじめ、多くの花々が春本番を告げるかのように咲き乱れていました。少し肌寒い空気でしたが、野山に咲く植物からは春の息吹を十分に実感できたひとときでした。
皆さんも春の空気を感じながら、先にも触れました現在実施中の「タンポポ調査・西日本2010」に参加してみませんか。
今回は一般市民の参加者を募り、西日本一帯で実施されているタンポポの分布調査「タンポポ調査・西日本2010」※に合わせて、この時期に花を咲かせるタンポポとその他の海浜植物、すみれや桜等の観察するイベントを本州最南端の潮岬にて開催しました。
※近年在来種(カンサイタンポポ、トウカイタンポポ等)と外来種(セイヨウタンポポ、アカミタンポポ等)の雑種が増え、在来種の減少が見られています。このような自然の変化について市民と一緒に広域的に調べるのが本調査の趣旨であり、環境省も後援しています。
詳細はこちら:http://www.nature.or.jp/Tampopo2010/
潮岬周辺は在来種のトウカイタンポポ(左)と外来種のセイヨウタンポポ(右)が自生しています。前者は夏にかけて他の植物によって日陰となってしまう場所に多く、後者は1年中開けた場所に多くみられます。
観察された様々な花々。春らしい色鮮やかさです。
左上:ウマゴヤシ マメ科、右上:ルリハコベ サクラソウ科、左下:ハマエンドウ マメ科、左下:フデリンドウ リンドウ科
ご紹介した花以外にもオオシマザクラやソメイヨシノの桜や、スミレやオカスミレ等のすみれをはじめ、多くの花々が春本番を告げるかのように咲き乱れていました。少し肌寒い空気でしたが、野山に咲く植物からは春の息吹を十分に実感できたひとときでした。
皆さんも春の空気を感じながら、先にも触れました現在実施中の「タンポポ調査・西日本2010」に参加してみませんか。
2010年03月19日可憐な花にも 【植物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
ここ熊野地域では、ソメイヨシノよりも一足先にヤマザクラやオオシマザクラが花を咲かせ、春うららかな光景が眼前に広がっています。
今日取り上げるすみれは春を彩る可憐な花として、桜に引けを取りません。現在この淡い紫色の小さな花々が、春の舞台で桜と共演しています。

タチツボスミレ スミレ科

ニオイタチツボスミレ スミレ科

ヒメスミレ スミレ科
上の写真がどれも同じに見えるかもしれませんが、すみれはよく似ていて、判別が難しい種が多いです。すみれの種子はアリが好むエライオソームと呼ばれる部分が付いていて、アリによって種子散布されます。アリの努力の成果として、コンクリートの割れ目の細い隙間に列を成して咲いていたりします。
独特の色合いと花びらをもった可憐な花にも、巧みな繁殖戦略が隠されています。
今日取り上げるすみれは春を彩る可憐な花として、桜に引けを取りません。現在この淡い紫色の小さな花々が、春の舞台で桜と共演しています。
タチツボスミレ スミレ科
ニオイタチツボスミレ スミレ科
ヒメスミレ スミレ科
上の写真がどれも同じに見えるかもしれませんが、すみれはよく似ていて、判別が難しい種が多いです。すみれの種子はアリが好むエライオソームと呼ばれる部分が付いていて、アリによって種子散布されます。アリの努力の成果として、コンクリートの割れ目の細い隙間に列を成して咲いていたりします。
独特の色合いと花びらをもった可憐な花にも、巧みな繁殖戦略が隠されています。
2010年03月10日春の野山でウオークラリー開催 【イベント】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
先日、宇久井ビジターセンターにて「春の野山でウオークラリー」を開催しました。開催前日は大荒れの天気で、当日も雨の予報で実施できるか心配していましたが、春の日差しが降り注ぐ好天の中、開催する事が出来ました!
この行事は、クイズやゲーム、指令などが所々に仕掛けられたビジターセンターの遊歩道をまわりながら、春を迎えて華やかになる自然を体感してもらう趣旨で行いました。
.JPG)
左)みんなでホルトの実探しの競争をしました。一番の子は90秒で、30個近くもゲットしました。
右)ホルトの木の実は最初緑色の果肉がついていますが、今頃は乾燥した梅干しの種のようになっています。

ネイチャービンゴは、現地で見ることが出来る色々な自然がマスの中に書かています。ビンゴを完成させるため、みんな熱心に自然探しをしてくれました。
このほかにも一人一人製作したマツの実を模した模型を飛ばして、その滞空時間の長さを競ったり、あらかじめ用意していた付け替え用の樹名板の木々を探したりと春の野山を舞台に楽しみました。
まだ冬の風物詩であるヤブツバキがあちらこちらで咲き乱れていた一方、スミレやジシバリ等の春の野花が同居している冬の面影の残った春の野山を感じることが出来ました。
この行事は、クイズやゲーム、指令などが所々に仕掛けられたビジターセンターの遊歩道をまわりながら、春を迎えて華やかになる自然を体感してもらう趣旨で行いました。
左)みんなでホルトの実探しの競争をしました。一番の子は90秒で、30個近くもゲットしました。
右)ホルトの木の実は最初緑色の果肉がついていますが、今頃は乾燥した梅干しの種のようになっています。
ネイチャービンゴは、現地で見ることが出来る色々な自然がマスの中に書かています。ビンゴを完成させるため、みんな熱心に自然探しをしてくれました。
このほかにも一人一人製作したマツの実を模した模型を飛ばして、その滞空時間の長さを競ったり、あらかじめ用意していた付け替え用の樹名板の木々を探したりと春の野山を舞台に楽しみました。
まだ冬の風物詩であるヤブツバキがあちらこちらで咲き乱れていた一方、スミレやジシバリ等の春の野花が同居している冬の面影の残った春の野山を感じることが出来ました。
2010年03月02日春の装い?【動物】
吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸
春に近づくにつれて、段々昼間に潮が大きく引く様になり、磯の観察をしやすい季節となってきました。
その干潮域から満潮域の間に位置する潮間帯と呼ばれる磯場にて見つけた、「これって春の装い?」と思った貝についてご紹介します。
下の写真のどこかに貝がいるのですが、分かりますでしょうか。

実はこの貝が隠れていました。

イボニシ アッキガイ科
一見岩場と見間違えるほどの変身ぶりでした。
早春から初夏にかけて、海藻が岩場や海底に生い茂ります。この時も岩などに海藻がびっしりとくっついていて、滑りそうになりました。
カニの中にはモクズショイと呼ばれる、自ら藻くずや砂などを身にまとい、カモフラージュするカニがいます。この貝は普通に磯場に生活している中で、海藻が周りに生い茂ってしまったのでしょうか。
これまで日記でご紹介してきた陸上だけではなく、磯においても生き物達の春の装いを感じる一コマでした。
その干潮域から満潮域の間に位置する潮間帯と呼ばれる磯場にて見つけた、「これって春の装い?」と思った貝についてご紹介します。
下の写真のどこかに貝がいるのですが、分かりますでしょうか。
実はこの貝が隠れていました。
イボニシ アッキガイ科
一見岩場と見間違えるほどの変身ぶりでした。
早春から初夏にかけて、海藻が岩場や海底に生い茂ります。この時も岩などに海藻がびっしりとくっついていて、滑りそうになりました。
カニの中にはモクズショイと呼ばれる、自ら藻くずや砂などを身にまとい、カモフラージュするカニがいます。この貝は普通に磯場に生活している中で、海藻が周りに生い茂ってしまったのでしょうか。
これまで日記でご紹介してきた陸上だけではなく、磯においても生き物達の春の装いを感じる一コマでした。

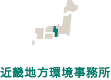
先日この日記上でもご案内した(※)、5月10日の地質の日を記念した自然観察会「地質の日フィールドワーク~太古の自然を感じよう、御浜小石の秘密をさぐれ!~」が開催されました。
前日まで悪天候が続き、天気が心配でしたが、当日は長時間日なたに居ると暑いほどの快晴に恵まれました。地質に関心のある方や親子連れで定員を超える盛況ぶりでした!
※2010年4月20日の日記「地質の日記念行事参加者募集中【イベント】」
七里御浜にて、フィールドワーク
浜辺を縦断してみると、場所によって石の種類が違います。波打ち際には厚みのある石が、逆に海から遠くなるとより薄い石が多くなっています。これは波のはたらきによって、石が仕分けられ、似た石が同じ場所に集まるためです。
またよく観察すると、石にも黒、赤、緑、白など様々な色があることに気づきます。これらの石はそれぞれでき方(成因)が違い、その成因によって名前がついています。
様々な色をした石
先生のお話によりますと、赤っぽい色をした石はチャートと呼ばれ、深海でプランクトンの死骸が堆積してできた石です。また、緑っぽい色をした石は玄武岩と呼ばれ、火山が噴火した時に流出したマグマが海底へ流れ、固まってできた石です。
1億年位前に形成され、現在地上で観察される状態にある石を見ていると、地球の躍動は凄いものがあるなあと感嘆せずにはいられません。
普段何気なく見ている石も、実はそこにたどりつくまでに興味深い変遷の歴史があるのですね。
講師の先生、ご参加の皆さん、ありがとうございました。