山陰海岸国立公園 竹野
326件の記事があります。
2013年05月22日草木のにおい【植物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
皆さんこんにちは竹野の酒井です。
季節は小満を迎え、竹野では初夏の雰囲気が漂っています。
先日ジオカヌーをしている最中に海に飛び込む機会があったのですが、
竹野の海はウェットスーツさえ着れば十分泳げる水温になっていました。
さて、5月18日に山陰海岸国立公園自然観察会「夕方お散歩ウォーキングジャジャ編」が行いました。今回は「香り」をテーマにした観察会としました。
観察会の詳細については後日、近畿地方環境事務所HPに掲載されると思いますのでここでは書きませんが、代わりに今回は植物観察における香りの楽しみ方について少し書きたいと思います。
植物の香りというと花の香りを思い浮かべる方が多いかとは思いますが、植物の香りは花だけではありません。

例えばクスノキ科の植物であるクスノキ(楠)やアブラチャン(油瀝青)、カシ(樫)の仲間などは葉を揉み込む事や、ライターで炙ってみる事によってスッとした香りが立ちます。

ヨモギ(蓬)は揉み込むと葉からは青臭いとも薬臭いとも何とも言い難い香りが漂います。

ニワトコ(接骨木)はちょっと変わった香りで葉をこするとピーナッツバターのような不思議な香りが立ちます。
それ以外にもマツやスギの樹液の香りやクヌギの腐ったお酢のような香り、笹の青々とした香りなど面白い香りの植物はたくさんあります。
植物以外でもシメジの仲間からはシメジの香りがしますし、マイタケの仲間からはマイタケの香りがします。
香りや味という物は非常に記憶に残りやすいものですので、どこで何を嗅いだ、食べたという記憶がずっと残ります。
山陰海岸国立公園に旅行に来られる方は是非、この植物の楽しみ方を実践してみてください。
何年か経った後、山陰海岸国立公園を思い出すためのタグとしても使うことができますので。
それでは今回はここまで。
季節は小満を迎え、竹野では初夏の雰囲気が漂っています。
先日ジオカヌーをしている最中に海に飛び込む機会があったのですが、
竹野の海はウェットスーツさえ着れば十分泳げる水温になっていました。
さて、5月18日に山陰海岸国立公園自然観察会「夕方お散歩ウォーキングジャジャ編」が行いました。今回は「香り」をテーマにした観察会としました。
観察会の詳細については後日、近畿地方環境事務所HPに掲載されると思いますのでここでは書きませんが、代わりに今回は植物観察における香りの楽しみ方について少し書きたいと思います。
植物の香りというと花の香りを思い浮かべる方が多いかとは思いますが、植物の香りは花だけではありません。

例えばクスノキ科の植物であるクスノキ(楠)やアブラチャン(油瀝青)、カシ(樫)の仲間などは葉を揉み込む事や、ライターで炙ってみる事によってスッとした香りが立ちます。

ヨモギ(蓬)は揉み込むと葉からは青臭いとも薬臭いとも何とも言い難い香りが漂います。

ニワトコ(接骨木)はちょっと変わった香りで葉をこするとピーナッツバターのような不思議な香りが立ちます。
それ以外にもマツやスギの樹液の香りやクヌギの腐ったお酢のような香り、笹の青々とした香りなど面白い香りの植物はたくさんあります。
植物以外でもシメジの仲間からはシメジの香りがしますし、マイタケの仲間からはマイタケの香りがします。
香りや味という物は非常に記憶に残りやすいものですので、どこで何を嗅いだ、食べたという記憶がずっと残ります。
山陰海岸国立公園に旅行に来られる方は是非、この植物の楽しみ方を実践してみてください。
何年か経った後、山陰海岸国立公園を思い出すためのタグとしても使うことができますので。
それでは今回はここまで。
2013年05月09日この貝殻が眼に入らぬかぁ~【動物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
皆さんこんにちは
竹野の酒井です。
5月に入ってだんだん暖かくなり、もう少しで海に入れそうです。
さて、今回の日記の本題ですが、皆さんは下の写真の貝殻をみて、何の生き物の貝殻かおわかりになりますでしょうか。

薄くて白い貝殻です。
これは・・・

アオイガイ(葵貝)という生き物の殻です。
これ実はタコの仲間で、カイダコ(貝蛸)と呼ばれる貝殻を持つ珍しいタコなんです。
貝殻はたまに海岸に漂着している物を見かけますが、生きた個体を見るのは初めてです。
定置網にかかっていたのを地元の漁師さんが竹野スノーケルセンターに持ってきてくれました。
貝殻の中に空気を入れて海面付近をぷかぷか浮かびながら移動する生き物とのこと。
タコなのに貝殻を持つ不思議な生き物です。
このような生き物と出会うことが出来るから生き物観察はやめられません。
さて、話は変わりますが、
5月18日に夕方お散歩ウォーキングの第2弾を開催いたします。
前回は休暇村竹野海岸周辺近畿自然歩道での観察会でしたが、今回は竹野浜のそばにあるジャジャ山公園にて行います。
参加費用は100円、当日の飛び込み参加もOKです。
是非是非皆さんご参加下さい。
それではまた次回。
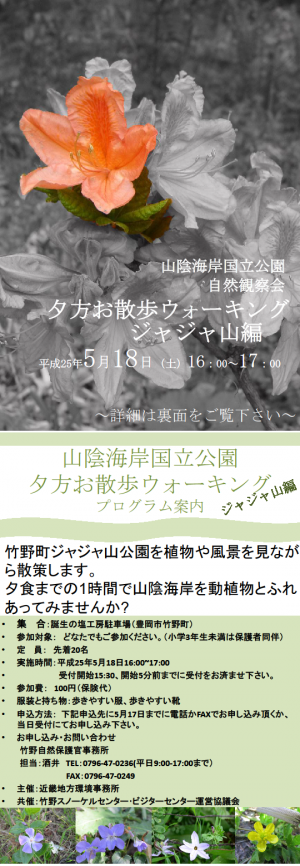
竹野の酒井です。
5月に入ってだんだん暖かくなり、もう少しで海に入れそうです。
さて、今回の日記の本題ですが、皆さんは下の写真の貝殻をみて、何の生き物の貝殻かおわかりになりますでしょうか。
薄くて白い貝殻です。
これは・・・
アオイガイ(葵貝)という生き物の殻です。
これ実はタコの仲間で、カイダコ(貝蛸)と呼ばれる貝殻を持つ珍しいタコなんです。
貝殻はたまに海岸に漂着している物を見かけますが、生きた個体を見るのは初めてです。
定置網にかかっていたのを地元の漁師さんが竹野スノーケルセンターに持ってきてくれました。
貝殻の中に空気を入れて海面付近をぷかぷか浮かびながら移動する生き物とのこと。
タコなのに貝殻を持つ不思議な生き物です。
このような生き物と出会うことが出来るから生き物観察はやめられません。
さて、話は変わりますが、
5月18日に夕方お散歩ウォーキングの第2弾を開催いたします。
前回は休暇村竹野海岸周辺近畿自然歩道での観察会でしたが、今回は竹野浜のそばにあるジャジャ山公園にて行います。
参加費用は100円、当日の飛び込み参加もOKです。
是非是非皆さんご参加下さい。
それではまた次回。
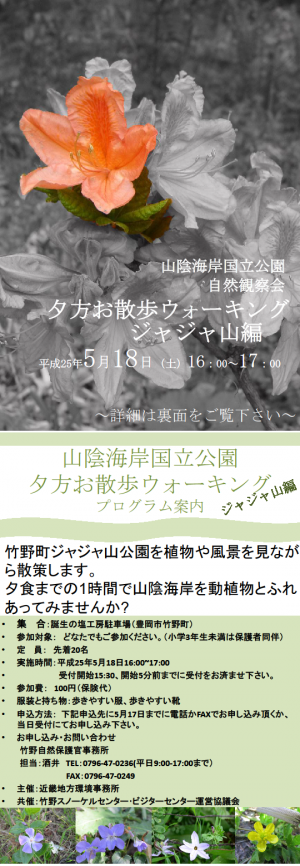
2013年04月26日お散歩ウォーキング!【イベント】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
AR日記 夕方お散歩ウォーキング
こんにちは竹野の酒井です。
季節は春真っ盛りですね。
スーパーの食材に春が旬の物が増え、辺りには春の花が咲き、何をするにも良い季節ですね。
さて、4月21日に山陰海岸国立公園自然観察会「夕方お散歩ウォーキング」を開催いたしました。
本来は20日に行われる予定の観察会でしたが雨天により翌日に繰り越されての開催となりました。
21日の天候は曇り、強風で気温も低く参加者が極端に少なくなるのではと危惧していましたが、14名のお客さんにご参加頂きました。

観察会実施前の説明を行っています。
手持ちホワイトボードとラネレート写真を使って、山陰海岸国立公園の概要と歩くルートのアナウンス、観察会で守って欲しい約束等々を説明していきます。

ヒメオドリコソウ(姫踊子草)の茎とキランソウ(金瘡子草)の茎のさわり比べをしています。
ヒメオドリコソウとキランソウは共にシソ科なのですが、キランソウはシソ科であるのに茎が丸い特徴を持っています。
さわり比べると一目瞭然です。
他にもヤブツバキ(藪椿)、ハマダイコン(浜大根)、イカリソウ(碇草)とトキワイカリソウ(常盤碇草)、ケキツネノボタン(毛狐の牡丹)等々の花を参加者の皆さんと一緒に観察しました。

展望台で凝灰角礫岩(ギョウカイカクレキガン)という岩石と風景の説明をしています。
凝灰角礫岩とは火山灰の中に角張った礫が埋まって凝結した岩のことです。
イメージとしては砕いたナッツを混ぜ込んだチョコレートのような構造でしょうか。
山陰海岸国立公園の特徴的な海岸地形を作っている岩石です。
ちなみにこの解説を行っている場所は小浦湾の上にある展望台なのですが、ここから辺りを良く眺めるとハート型の岩が見えるポイントです。
その後休暇村のロビーまで戻ってぴったり1時間で終了です。
ちなみに次回の夕方お散歩ウォークは5月18日(土)に行われる予定です。
場所は休暇村から離れて竹野町にあるジャジャ山公園を散策いたします。
詳細についてはまた次回の日記でご案内させて頂こうかと思います。
こんにちは竹野の酒井です。
季節は春真っ盛りですね。
スーパーの食材に春が旬の物が増え、辺りには春の花が咲き、何をするにも良い季節ですね。
さて、4月21日に山陰海岸国立公園自然観察会「夕方お散歩ウォーキング」を開催いたしました。
本来は20日に行われる予定の観察会でしたが雨天により翌日に繰り越されての開催となりました。
21日の天候は曇り、強風で気温も低く参加者が極端に少なくなるのではと危惧していましたが、14名のお客さんにご参加頂きました。
観察会実施前の説明を行っています。
手持ちホワイトボードとラネレート写真を使って、山陰海岸国立公園の概要と歩くルートのアナウンス、観察会で守って欲しい約束等々を説明していきます。

ヒメオドリコソウ(姫踊子草)の茎とキランソウ(金瘡子草)の茎のさわり比べをしています。
ヒメオドリコソウとキランソウは共にシソ科なのですが、キランソウはシソ科であるのに茎が丸い特徴を持っています。
さわり比べると一目瞭然です。
他にもヤブツバキ(藪椿)、ハマダイコン(浜大根)、イカリソウ(碇草)とトキワイカリソウ(常盤碇草)、ケキツネノボタン(毛狐の牡丹)等々の花を参加者の皆さんと一緒に観察しました。

展望台で凝灰角礫岩(ギョウカイカクレキガン)という岩石と風景の説明をしています。
凝灰角礫岩とは火山灰の中に角張った礫が埋まって凝結した岩のことです。
イメージとしては砕いたナッツを混ぜ込んだチョコレートのような構造でしょうか。
山陰海岸国立公園の特徴的な海岸地形を作っている岩石です。
ちなみにこの解説を行っている場所は小浦湾の上にある展望台なのですが、ここから辺りを良く眺めるとハート型の岩が見えるポイントです。
その後休暇村のロビーまで戻ってぴったり1時間で終了です。
ちなみに次回の夕方お散歩ウォークは5月18日(土)に行われる予定です。
場所は休暇村から離れて竹野町にあるジャジャ山公園を散策いたします。
詳細についてはまた次回の日記でご案内させて頂こうかと思います。
2013年04月10日蛇って肉食なので苺食べるわけないのですよね【植物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
こんにちは竹野の酒井です。
季節は清明を迎え、すがすがしい春の気候となりました。サクラもほぼ満開。
もう出勤時にコートはいりませんし、業務中にコートを着る必要もなくなり、
厚着が嫌いな私は喜んでおります。
さて先日猫崎半島に巡視に行ってきました。
その際に見つけた植物をいくつかご紹介します。

シロバナノヘビイチゴ(白花の蛇苺)
ヘビイチゴの仲間です。なぜか一輪だけ咲いていました。
ちなみにヘビイチゴは名前の由来がはっきりしない植物で
「ヘビが食べるイチゴ」「ヘビぐらいしか食べないくらい不味いイチゴ」等々、文献によって記述が違います。
ヘビイチゴの名前の正式な由来を知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
次の花はアオキ(青木)
常緑低木であり、また観葉植物として有名な樹木です。
冬期は長細いサクランボのような実をつけるため、それを観賞するために栽培している方もいらっしゃると思いますが、実だけではなく花も悪くありません。
蝶のブローチのような紫色の花をつけますのでそれを是非観賞して頂きたいです。

黄色い花のキジムシロ(雉蓆)
春によく見かける花ですね。
黄色くて葉が三つ葉で、すきっ歯のような5弁の花びらが特徴的な花です。
そして最後にヤマザクラです。
現在ではほとんど散ってしまっていますが
中々に綺麗な花見のポイントです。
皆様も桜の時期には是非猫崎半島を訪れてみて下さい。
さて、いくつか植物をご紹介いたしましたが、
今回の日記はここからが本題です。
竹野自然保護官事務所では
4月20日(土)16:00から1時間、自然観察会を実施いたします。
場所は休暇村竹野海岸周辺の近畿自然歩道で当日参加OK、参加料金100円の散歩感覚で気軽に参加できる観察会です。
詳しい情報は下記の画像もしくは
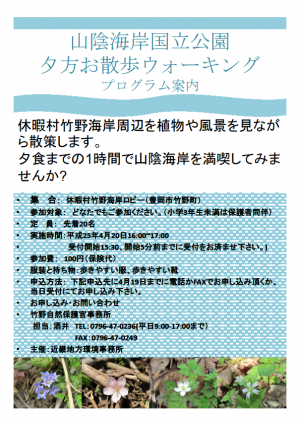
竹野自然保護官事務所
Tel.0796-47-0236 担当 酒井
までお気軽にお電話下さい。
季節は清明を迎え、すがすがしい春の気候となりました。サクラもほぼ満開。
もう出勤時にコートはいりませんし、業務中にコートを着る必要もなくなり、
厚着が嫌いな私は喜んでおります。
さて先日猫崎半島に巡視に行ってきました。
その際に見つけた植物をいくつかご紹介します。

シロバナノヘビイチゴ(白花の蛇苺)
ヘビイチゴの仲間です。なぜか一輪だけ咲いていました。
ちなみにヘビイチゴは名前の由来がはっきりしない植物で
「ヘビが食べるイチゴ」「ヘビぐらいしか食べないくらい不味いイチゴ」等々、文献によって記述が違います。
ヘビイチゴの名前の正式な由来を知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
次の花はアオキ(青木)
常緑低木であり、また観葉植物として有名な樹木です。
冬期は長細いサクランボのような実をつけるため、それを観賞するために栽培している方もいらっしゃると思いますが、実だけではなく花も悪くありません。
蝶のブローチのような紫色の花をつけますのでそれを是非観賞して頂きたいです。

黄色い花のキジムシロ(雉蓆)
春によく見かける花ですね。
黄色くて葉が三つ葉で、すきっ歯のような5弁の花びらが特徴的な花です。
そして最後にヤマザクラです。
現在ではほとんど散ってしまっていますが
中々に綺麗な花見のポイントです。
皆様も桜の時期には是非猫崎半島を訪れてみて下さい。
さて、いくつか植物をご紹介いたしましたが、
今回の日記はここからが本題です。
竹野自然保護官事務所では
4月20日(土)16:00から1時間、自然観察会を実施いたします。
場所は休暇村竹野海岸周辺の近畿自然歩道で当日参加OK、参加料金100円の散歩感覚で気軽に参加できる観察会です。
詳しい情報は下記の画像もしくは
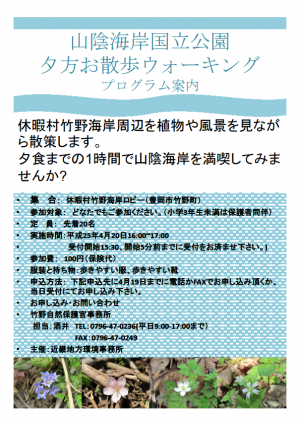
竹野自然保護官事務所
Tel.0796-47-0236 担当 酒井
までお気軽にお電話下さい。
2013年03月18日雑草という名の草は無いと誰かが言っていました【植物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
皆さんこんにちは。竹野の酒井です。
竹野では梅の花に桃の花が咲いております。
春本番になったかと思い、コートを着ずに出かけたところ、暖かさの振り戻しが来たかのような冬日なってしまい、季節の変わり目の天気は読みづらいと実感しております。
梅や桃以外の花もいろいろと咲きはじめておりますので、今回は道端に生えている“雑草”とくくられてしまいそうな花々を紹介いたします。
まずはこちら

オオイヌノフグリ(大犬の陰囊)
私が思うに多分…日本で1番かわいそうな名前がついている植物です。
2番目はヘクソカズラ(屁糞葛)かハキダメギク(掃溜菊)かでしょうか…
動物ならリュウキュウトカゲモドキ(琉球蜥蜴擬)もかわいそうな名前ですが…
ちなみになぜオオイヌノフグリにこのような名前がついているのかというと、イヌノフグリ(犬の陰囊)という植物のとばっちりを受けたからというのが理由です。詳細は是非皆さんで調べてみて下さい。
さて、名前はちょっとアレなこの花ですが、花自体は楚々とした綺麗な青色をしており、
ルーペ等で拡大して眺めてみるとなかなかです。こういった拡大をしてみないと良さが分かりにくい花は多いので、是非こうした小さな花はルーペ等を使って眺めてみて頂きたいと思います。個人的には亜高山帯に生えるクロクモソウ(黒雲草)などがオススメです。
ちなみにこの植物、綺麗な花をつけるのですが、実は外来種なので気持ちとしては少し複雑です…

次に紹介する物はホトケノザ(仏の座)です。
これも道端に生えていることが多いですので皆さんも見たことが多いのではないでしょうか。
紫色のシソ科の花です。以前にも日記で書いたかもしれませんが、シソ科の植物の特徴は茎が四角い事です。見つけましたら、茎を触って転がしてみましょう。ちなみに花からは蜜が吸えます。吸うと微かに甘みがあります。
味を例えるならば、グラス一杯の水にガムシロップを一滴垂らした飲み物のようなものでしょうか。非常に微かな甘みです
同じ花の蜜ならばハイビスカスやツツジの方が多分美味しいと思います。(ただし有毒のレンゲツツジ(蓮華躑躅)を除きます。)
最後は

サザンカ(山茶花)
山茶花山茶花咲いた道~♪のサザンカです。
サザンカはツバキ(椿)の仲間で見た目も非常にツバキによく似ていますが、ツバキのように首が落ちるような花の散り方をせず花弁がばらばらになって散るのが特徴です。冬の屋外でも咲いている貴重な花で、よく生け垣などに使用されています。
冬の花は観察する際の周囲のシチュエーションがとても良いと思います。辺りが虫や鳥の声で賑やかな夏の花を観察するのももちろん良いですが、周囲の木の葉が落ちて虫の声も無い、静かにただ咲いている冬の花の様子もとても良い物です。
といったところで今回の日記はここまでです。
春になり、花咲き始めて嬉しい限りです。
竹野では梅の花に桃の花が咲いております。
春本番になったかと思い、コートを着ずに出かけたところ、暖かさの振り戻しが来たかのような冬日なってしまい、季節の変わり目の天気は読みづらいと実感しております。
梅や桃以外の花もいろいろと咲きはじめておりますので、今回は道端に生えている“雑草”とくくられてしまいそうな花々を紹介いたします。
まずはこちら
オオイヌノフグリ(大犬の陰囊)
私が思うに多分…日本で1番かわいそうな名前がついている植物です。
2番目はヘクソカズラ(屁糞葛)かハキダメギク(掃溜菊)かでしょうか…
動物ならリュウキュウトカゲモドキ(琉球蜥蜴擬)もかわいそうな名前ですが…
ちなみになぜオオイヌノフグリにこのような名前がついているのかというと、イヌノフグリ(犬の陰囊)という植物のとばっちりを受けたからというのが理由です。詳細は是非皆さんで調べてみて下さい。
さて、名前はちょっとアレなこの花ですが、花自体は楚々とした綺麗な青色をしており、
ルーペ等で拡大して眺めてみるとなかなかです。こういった拡大をしてみないと良さが分かりにくい花は多いので、是非こうした小さな花はルーペ等を使って眺めてみて頂きたいと思います。個人的には亜高山帯に生えるクロクモソウ(黒雲草)などがオススメです。
ちなみにこの植物、綺麗な花をつけるのですが、実は外来種なので気持ちとしては少し複雑です…
次に紹介する物はホトケノザ(仏の座)です。
これも道端に生えていることが多いですので皆さんも見たことが多いのではないでしょうか。
紫色のシソ科の花です。以前にも日記で書いたかもしれませんが、シソ科の植物の特徴は茎が四角い事です。見つけましたら、茎を触って転がしてみましょう。ちなみに花からは蜜が吸えます。吸うと微かに甘みがあります。
味を例えるならば、グラス一杯の水にガムシロップを一滴垂らした飲み物のようなものでしょうか。非常に微かな甘みです
同じ花の蜜ならばハイビスカスやツツジの方が多分美味しいと思います。(ただし有毒のレンゲツツジ(蓮華躑躅)を除きます。)
最後は
サザンカ(山茶花)
山茶花山茶花咲いた道~♪のサザンカです。
サザンカはツバキ(椿)の仲間で見た目も非常にツバキによく似ていますが、ツバキのように首が落ちるような花の散り方をせず花弁がばらばらになって散るのが特徴です。冬の屋外でも咲いている貴重な花で、よく生け垣などに使用されています。
冬の花は観察する際の周囲のシチュエーションがとても良いと思います。辺りが虫や鳥の声で賑やかな夏の花を観察するのももちろん良いですが、周囲の木の葉が落ちて虫の声も無い、静かにただ咲いている冬の花の様子もとても良い物です。
といったところで今回の日記はここまでです。
春になり、花咲き始めて嬉しい限りです。
2013年03月11日ひふみ?【動物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
季節は啓蟄をこえ、海はベタ凪ぎで天候も暖かく安定してきました。
海は凪が多くなり、ウェットをさえしっかり着れば海に入れそうな気温が続いています。
さて啓蟄と聞くと私いつも古い新聞の4コマ漫画を思い出します。
冬眠中のモグラが2月半ばの陽気に誘われて、つい地上に出て行こうとしたところを啓蟄はまだ先だぞと仲間が引き留める、そんな話でした。
そのような漫画の状況と似たような状況に遭遇しました。

啓蟄までは後3週間近く日がある2月19日の出来事です。
休暇村竹野海岸のキャンプ場の芝生なのですが、道路と芝生の境目辺りがもこもこと盛り上がっています。
啓蟄はまだ先ですが、気の早いモグラが活動を始めたようです。
このもこもこはモグラ塚というモグラが地下を通った後です。
別の地点では…

芝生の中をうねうねとモグラ穴が通っています。
多分このモグラ穴を作ったのはこの種類ではないかと思います。

ヒミズ(日不見)です。比較的地面の浅いところに生息しているモグラです。(なお写真は山陰でとった物ではなく、長野県で撮影した物です。)
名前の由来は諸説あるのですが、ヒミズは夜行性で日中は土の中に潜っているため、“日”光を“見ず”という説とモグラは地面にずっと潜っているのは地上に出ると太陽を浴びると死んでしまうと昔は思われていたため、一生“日”の光を“見”ることが“不”可能。だと思われていたことから名前がついたと言われています。
もちろん日の光に当たっても死にはしません。
余談ですが私はこの種類には【ひふみん】とあだ名をつけています。
あだ名由来は…そのままですね。
モグラ塚は森の遊歩道や神社の境内などでたまに見られますので、よろしければ皆さんも探してみてください。
海は凪が多くなり、ウェットをさえしっかり着れば海に入れそうな気温が続いています。
さて啓蟄と聞くと私いつも古い新聞の4コマ漫画を思い出します。
冬眠中のモグラが2月半ばの陽気に誘われて、つい地上に出て行こうとしたところを啓蟄はまだ先だぞと仲間が引き留める、そんな話でした。
そのような漫画の状況と似たような状況に遭遇しました。

啓蟄までは後3週間近く日がある2月19日の出来事です。
休暇村竹野海岸のキャンプ場の芝生なのですが、道路と芝生の境目辺りがもこもこと盛り上がっています。
啓蟄はまだ先ですが、気の早いモグラが活動を始めたようです。
このもこもこはモグラ塚というモグラが地下を通った後です。
別の地点では…

芝生の中をうねうねとモグラ穴が通っています。
多分このモグラ穴を作ったのはこの種類ではないかと思います。

ヒミズ(日不見)です。比較的地面の浅いところに生息しているモグラです。(なお写真は山陰でとった物ではなく、長野県で撮影した物です。)
名前の由来は諸説あるのですが、ヒミズは夜行性で日中は土の中に潜っているため、“日”光を“見ず”という説とモグラは地面にずっと潜っているのは地上に出ると太陽を浴びると死んでしまうと昔は思われていたため、一生“日”の光を“見”ることが“不”可能。だと思われていたことから名前がついたと言われています。
もちろん日の光に当たっても死にはしません。
余談ですが私はこの種類には【ひふみん】とあだ名をつけています。
あだ名由来は…そのままですね。
モグラ塚は森の遊歩道や神社の境内などでたまに見られますので、よろしければ皆さんも探してみてください。
2013年03月01日赤い体のイカしたヤツ【動物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
皆さんこんにちは。
竹野の酒井です。
最近はずいぶんと日が長くなり、春に近づいていると感じます。
それを裏付けるかのように先日行った蕎麦屋さんのお品書きにはふきのとうの天ぷらがのっていました。
季節の食べ物を食べるとその季節になったことを実感しますね。
さて、先日竹野スノーケルセンタービジターセンターに行った時のことですが、
ふと空を見上げるとカモメが海岸沿いをひたすらぐるぐると旋回していました。
大浦湾で鳥が周囲を離れず、奇妙な飛び方をしている場合には海岸沿いに“何か”がある可能性が高いです。
海岸を見回ってみると

でろんと、アカイカが漂着していました。かなり大きなサイズです。
ちなみにまだ生きています。
しかし、よく見ると胴体の先端部分が鳥によってかじられ、目が一つなくなっています。

大きさが分かりづらいので私の足を隣に置いてみました。
靴の「全長」は30cmほどですので外套長(イカの胴体部分)の長さは大体50cmほどでしょうか。
ちなみに「胴体の部分が50cmのアカイカなんて私が知っているアカイカじゃない!」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
実は一般にアカイカと呼ばれている種は三種類ありまして、
アカイカ科のアカイカ、ヤリイカ科のケンサキイカ、ソデイカ科のソデイカがそれぞれ「あかいか」や「アカイカ」の標記でスーパーなどで売られています。
もちろん、この写真のイカはアカイカ科のアカイカです。

たらいに入れてみるとこのような感じです。
想像通り、外套長は50cmほどでした。
持ってみるとずしりと重く、吸盤がよく吸い付いてきます。
こういう物おもしろい物がたまに流れ着くので海岸巡視はやめられません。
皆さんも是非海岸をのぞいてみてください。
たまにとんでもない物が流れ着いたりしていますよ。
竹野の酒井です。
最近はずいぶんと日が長くなり、春に近づいていると感じます。
それを裏付けるかのように先日行った蕎麦屋さんのお品書きにはふきのとうの天ぷらがのっていました。
季節の食べ物を食べるとその季節になったことを実感しますね。
さて、先日竹野スノーケルセンタービジターセンターに行った時のことですが、
ふと空を見上げるとカモメが海岸沿いをひたすらぐるぐると旋回していました。
大浦湾で鳥が周囲を離れず、奇妙な飛び方をしている場合には海岸沿いに“何か”がある可能性が高いです。
海岸を見回ってみると
でろんと、アカイカが漂着していました。かなり大きなサイズです。
ちなみにまだ生きています。
しかし、よく見ると胴体の先端部分が鳥によってかじられ、目が一つなくなっています。
大きさが分かりづらいので私の足を隣に置いてみました。
靴の「全長」は30cmほどですので外套長(イカの胴体部分)の長さは大体50cmほどでしょうか。
ちなみに「胴体の部分が50cmのアカイカなんて私が知っているアカイカじゃない!」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
実は一般にアカイカと呼ばれている種は三種類ありまして、
アカイカ科のアカイカ、ヤリイカ科のケンサキイカ、ソデイカ科のソデイカがそれぞれ「あかいか」や「アカイカ」の標記でスーパーなどで売られています。
もちろん、この写真のイカはアカイカ科のアカイカです。
たらいに入れてみるとこのような感じです。
想像通り、外套長は50cmほどでした。
持ってみるとずしりと重く、吸盤がよく吸い付いてきます。
こういう物おもしろい物がたまに流れ着くので海岸巡視はやめられません。
皆さんも是非海岸をのぞいてみてください。
たまにとんでもない物が流れ着いたりしていますよ。
2013年02月13日猫崎かんじきハイク!!~実施編~【イベント】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
皆さんこんにちは
竹野の酒井です。
二月になり、なぜか春のような暖かい日が続いています。
まだまだ啓蟄も先なのですが妙に暖かいですね。
冬眠していた動物が寝ぼけて外に出てきそうな気温です。
さて、以前よりこの日記でも告知しておりました竹野自然保護官事務所主催の冬のイベント。
「猫崎半島ハイキング~自家製かんじきであるいてみよう!~」
が1月26日に開催されました。
今回その様子をいくつかご紹介します。
今回のイベントは竹野町にある「誕生の塩工房」という普段は日本海の海水を使って、塩作り体験教室を行っている工房の場所をお借りして実施しました。
当日の天気はかんじきで歩くにはもってこいの雪模様、というよりも吹雪でした。
スタートから天気に好かれているのか嫌われているか分かりません。

そのような天気の中イベントスタートです。
開会挨拶後、早速かんじき作成に入ります。
丸のままの竹を割り、細長く、うすく鉈で削っていきます。
炭火でじっくり加熱します。
竹を曲げるには、お湯で煮る、蒸気で蒸す、加熱した金属に当てる等、いろいろな方法があるのですが、今回は炭火で炙る方法で竹を曲げました。
この曲げ工程が、かんじき作りで一番大変で難しい所です。

曲げ工程が終われば次は仕上げ作業です。
紐を編み込み足置き場をつくります。
十分に紐を編み込んでほどけないようにした後、足とかんじきを固定する紐をくくりつければかんじきは完成です。
こうして文字に書き起こすと案外あっさり完成しているように聞こえますが実際にはスタートから完成まで4時間以上かかっています。
完成までにこれほどに時間がかかると疲れて大変ではないだろうかと参加者の皆さんに感想を聞いてみると「手間はかかるが楽しい」という答えが返ってきました。
好評だったようです。
そうそう、作業中に昼食も頂きました。
ハタハタの干物と炊きたてご飯のおにぎりとお味噌汁です。
脂がよくのったハタハタは大変美味しかったです。

さて、かんじきが完成した後は外に出て観察会を行います。
今回の観察会のタイトルは
「“猫崎半島”かんじきハイキング」でしたが、外は吹雪と高波という悪天候で猫崎半島までの移動を断念し、作業を行っていた誕生の塩工房の裏手にありますジャジャ山公園で観察会を行いました。
豪雪でしたがシカの足跡、シカの食痕、クマの爪痕、キノコなど様々な物を見ることが出来ました。
その後は塩工房まで戻り、冷えた体を温めながら解散の挨拶を行い、終了となりました。
次回は…近畿自然歩道を使った観察会、イベントを計画中です。
3月か4月ぐらいに実施しようかと思いただいま企画を作成中です。
企画が完成し次第ご報告いたします。
それではまた次回。
竹野の酒井です。
二月になり、なぜか春のような暖かい日が続いています。
まだまだ啓蟄も先なのですが妙に暖かいですね。
冬眠していた動物が寝ぼけて外に出てきそうな気温です。
さて、以前よりこの日記でも告知しておりました竹野自然保護官事務所主催の冬のイベント。
「猫崎半島ハイキング~自家製かんじきであるいてみよう!~」
が1月26日に開催されました。
今回その様子をいくつかご紹介します。
今回のイベントは竹野町にある「誕生の塩工房」という普段は日本海の海水を使って、塩作り体験教室を行っている工房の場所をお借りして実施しました。
当日の天気はかんじきで歩くにはもってこいの雪模様、というよりも吹雪でした。
スタートから天気に好かれているのか嫌われているか分かりません。

そのような天気の中イベントスタートです。
開会挨拶後、早速かんじき作成に入ります。
丸のままの竹を割り、細長く、うすく鉈で削っていきます。
炭火でじっくり加熱します。
竹を曲げるには、お湯で煮る、蒸気で蒸す、加熱した金属に当てる等、いろいろな方法があるのですが、今回は炭火で炙る方法で竹を曲げました。
この曲げ工程が、かんじき作りで一番大変で難しい所です。

曲げ工程が終われば次は仕上げ作業です。
紐を編み込み足置き場をつくります。
十分に紐を編み込んでほどけないようにした後、足とかんじきを固定する紐をくくりつければかんじきは完成です。
こうして文字に書き起こすと案外あっさり完成しているように聞こえますが実際にはスタートから完成まで4時間以上かかっています。
完成までにこれほどに時間がかかると疲れて大変ではないだろうかと参加者の皆さんに感想を聞いてみると「手間はかかるが楽しい」という答えが返ってきました。
好評だったようです。
そうそう、作業中に昼食も頂きました。
ハタハタの干物と炊きたてご飯のおにぎりとお味噌汁です。
脂がよくのったハタハタは大変美味しかったです。

さて、かんじきが完成した後は外に出て観察会を行います。
今回の観察会のタイトルは
「“猫崎半島”かんじきハイキング」でしたが、外は吹雪と高波という悪天候で猫崎半島までの移動を断念し、作業を行っていた誕生の塩工房の裏手にありますジャジャ山公園で観察会を行いました。
豪雪でしたがシカの足跡、シカの食痕、クマの爪痕、キノコなど様々な物を見ることが出来ました。
その後は塩工房まで戻り、冷えた体を温めながら解散の挨拶を行い、終了となりました。
次回は…近畿自然歩道を使った観察会、イベントを計画中です。
3月か4月ぐらいに実施しようかと思いただいま企画を作成中です。
企画が完成し次第ご報告いたします。
それではまた次回。
2013年01月28日フィールドサインと正体不明【動物】
山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明
皆さんこんにちは。
竹野の酒井です。
季節は大寒を迎え、暦の上では寒さは折り返し地点を迎えたようです。
とはいえ、折り返し地点を過ぎただけですので、結局の所寒いことに変わりはありませんが。
さて、前置きはこの辺にいたしまして、先日猫崎半島まで巡視に行ってきました。
その際に見つけた物をいくつかご紹介します。
まずはこちら

ニホンジカ(日本鹿)の角研ぎ跡とテン(貂)の糞です。
シカの角研ぎ跡については賀嶋公園のサクラの木についていました。
シカというのは一年で角が生え替わる生物です。
角が生える時期になると徐々に頭皮の下で角が成長し、角が頭皮にくるまれたような形になります。
十分に角が成長した後シカは木に角をこすりつけて、角をくるんでいる皮を剥いでしまいます。
その角の皮剥ぎに使われた木の樹皮にはこのような傷が残ります。
ちなみに、鹿が樹皮を食べるときは角研ぎとはとは違い、樹皮がこうして繊維状に傷がつくことはなく、食べたところだけ綺麗に削ったような跡になります。
次にテンの糞について見てみましょう。
テンは雑食ですので糞を見てみると植物と動物の未消化物がまざっています。(この写真では何かの種子と鳥の羽根が混ざっています。)
また、テンという生物は縄張りを示すためにこういった岩やベンチといった目立つ場所に”わざわざ”糞をします。
登山中に山の風景や花などを見ようとよく足下を見ずに歩いて行くと踏んづけてしまう糞の代表格です。皆さん山道を歩かれる際はお気をつけて。

こちらはビジョオニグモ(美女鬼蜘蛛)の卵嚢とカワラタケ(瓦茸)。
上の写真の真ん中には白いクモの糸がびっしりとついています。
この葉っぱの裏にはこのクモの卵があります。(ちょっとグロテスクなので写真は載せませんでしたが…)
生物が越冬する方法はいくつかありますが、(冬眠する、暖かい所まで移動するなど)
このクモは卵の状態で冬を越します。冬の間卵のままでいれば、エネルギーも消費せず、食料もいらないという訳です。
生物の仕組みという物は本当によくできていると常々思います。
カワラタケについては写真のベンチをよく見てみると細かい灰色っぽいものがいくつもいくつも生えていることが分かります。
見ての通り小さいキノコですし、毒はありませんが非常に固いキノコですので食べられません。
(ちなみに私は昔、毒キノコではないことを十分に確認してから食べてみたことがあるのですが、非常に固く、鉋くずやコルクの破片をかじっているようなそんな食感でした。また、キノコの素人判断は大変危険です。キノコ狩りや、山野から取ってきたキノコを食べる際はちゃんと専門の方の意見を聞き、それに従いましょう。)
食べられないキノコではありますがこのキノコからは抗がん剤の材料を取る事が出来ます。
地味ですが意外とすごい、そのようなキノコです。

そして今回見つけた一番不思議な物がこちら。
謎のゼリー状の物質です。
落ちていた木の枝でつついて見た所、ゼリー飲料程度の堅さと、唾液程度の粘りを持つ物体であることは分かりましたので、粘菌の変形体ではないかと予想はしています。
ただ、菌類はキノコ以外私の専門外ですので、確証はありません。
もしこれが何であるか分かる方いらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
といったところで今回の日記はこの辺でおしまいにしたいと思います。
それではまた次回。
竹野の酒井です。
季節は大寒を迎え、暦の上では寒さは折り返し地点を迎えたようです。
とはいえ、折り返し地点を過ぎただけですので、結局の所寒いことに変わりはありませんが。
さて、前置きはこの辺にいたしまして、先日猫崎半島まで巡視に行ってきました。
その際に見つけた物をいくつかご紹介します。
まずはこちら

ニホンジカ(日本鹿)の角研ぎ跡とテン(貂)の糞です。
シカの角研ぎ跡については賀嶋公園のサクラの木についていました。
シカというのは一年で角が生え替わる生物です。
角が生える時期になると徐々に頭皮の下で角が成長し、角が頭皮にくるまれたような形になります。
十分に角が成長した後シカは木に角をこすりつけて、角をくるんでいる皮を剥いでしまいます。
その角の皮剥ぎに使われた木の樹皮にはこのような傷が残ります。
ちなみに、鹿が樹皮を食べるときは角研ぎとはとは違い、樹皮がこうして繊維状に傷がつくことはなく、食べたところだけ綺麗に削ったような跡になります。
次にテンの糞について見てみましょう。
テンは雑食ですので糞を見てみると植物と動物の未消化物がまざっています。(この写真では何かの種子と鳥の羽根が混ざっています。)
また、テンという生物は縄張りを示すためにこういった岩やベンチといった目立つ場所に”わざわざ”糞をします。
登山中に山の風景や花などを見ようとよく足下を見ずに歩いて行くと踏んづけてしまう糞の代表格です。皆さん山道を歩かれる際はお気をつけて。

こちらはビジョオニグモ(美女鬼蜘蛛)の卵嚢とカワラタケ(瓦茸)。
上の写真の真ん中には白いクモの糸がびっしりとついています。
この葉っぱの裏にはこのクモの卵があります。(ちょっとグロテスクなので写真は載せませんでしたが…)
生物が越冬する方法はいくつかありますが、(冬眠する、暖かい所まで移動するなど)
このクモは卵の状態で冬を越します。冬の間卵のままでいれば、エネルギーも消費せず、食料もいらないという訳です。
生物の仕組みという物は本当によくできていると常々思います。
カワラタケについては写真のベンチをよく見てみると細かい灰色っぽいものがいくつもいくつも生えていることが分かります。
見ての通り小さいキノコですし、毒はありませんが非常に固いキノコですので食べられません。
(ちなみに私は昔、毒キノコではないことを十分に確認してから食べてみたことがあるのですが、非常に固く、鉋くずやコルクの破片をかじっているようなそんな食感でした。また、キノコの素人判断は大変危険です。キノコ狩りや、山野から取ってきたキノコを食べる際はちゃんと専門の方の意見を聞き、それに従いましょう。)
食べられないキノコではありますがこのキノコからは抗がん剤の材料を取る事が出来ます。
地味ですが意外とすごい、そのようなキノコです。

そして今回見つけた一番不思議な物がこちら。
謎のゼリー状の物質です。
落ちていた木の枝でつついて見た所、ゼリー飲料程度の堅さと、唾液程度の粘りを持つ物体であることは分かりましたので、粘菌の変形体ではないかと予想はしています。
ただ、菌類はキノコ以外私の専門外ですので、確証はありません。
もしこれが何であるか分かる方いらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
といったところで今回の日記はこの辺でおしまいにしたいと思います。
それではまた次回。

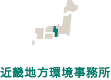
近畿地方は梅雨入りし、カビ、湿気と戦わなくてはならない季節がやってきました。
じめじめと洗濯物が乾かず嫌な季節ですが、梅雨が来るたびに米農家であった祖父の「梅雨がなければ商売あがったりだぁ」という言葉を思い出します。
お米のためなら梅雨の不快感もしかたないですね。
さて、前置きはこの辺にいたしまして、香美町香住区の海岸沿いを巡視する機会がありましたので、今回はその様子をお伝えしたいと思います。
山陰海岸国立公園は地形と岩石の公園と呼ばれておりますが、香住の海岸沿いには、これぞ山陰海岸!と言いたくなるような、奇岩、地層、地形等がたくさんあります。
今回巡視を行った場所で特に有名な物をあげるならば・・・
鎧の袖。
国の天然記念物、日本百景にもなっている場所ですが、日本の鎧の肩から肘にかけての袖の部分に似ている事からその名前がついたと言われています。
鶏のささみのような柱状節理にレゴブロックを積み重ねたような板状節理が合わさってこのような形になっています。
高さは200m、傾斜は70°にもなるため、船の上から見あげると写真で見る以上の迫力です。
インディアン島というネイティブアメリカンの酋長さんのような形の岩です。
どのあたりがインディアンのようなのかと思う方は三色の囲み付き写真をご覧ください。
私も最初はどこがネイティブアメリカンなのか良くわかりませんでしたが、じっくり見てみるとみれば見るほどネイティブアメリカンです。
個人的に最も気に入っているポイントがこちら。百層崖という地層を観察するにはもってこいの場所なのですが、注目すべきはこの写真の中央、ふたつの穴が空いています。
山陰海岸にはメガネ島という、メガネのように2つの穴の空いた岩があるのですがこの場所はそれ以上にメガネです。セルフレームの四角いメガネそのままの形をしています。
普段は陸から海岸を見る巡視を行っていますが、海から海岸を見ると、視点の角度、高さが変わるため、巡視で見慣れている風景でも、非常にダイナミックに感じます。
夏に山陰海岸にご旅行にいらっしゃる皆さんは、海から山陰海岸を眺めるというプランを検討されてはいかがでしょうか。
竹野スノーケルセンターではカヌー体験、竹野、香住、浦富などの場所では遊覧船が運行しております。
是非一度海から見る山陰海岸国立公園をお試しください。