吉野熊野国立公園
71件の記事があります。
2019年01月08日初日の出
吉野熊野国立公園 熊野 岩田佐知代
アクティブ・レンジャーの岩田です。
新しい年が始まりましたね。
皆さんそれぞれの場所で新年の初日の出を見たり、初詣に行きお祈りをされたことと思います。
吉野熊野国立公園の熊野・田辺エリアは太平洋に面しているため、日の出スポットはたくさんありますが、私が毎年欠かさず海岸沿いに出て見ている御浜町の初日の出を紹介します。
御浜町の七里御浜には、今年も大勢の人が初日の出を見に来ていました。
水平線に雲がかかってなかなか太陽が出てこない年もありますが、今年は少し雲がかかっていたものの、無事、初日の出を見ることができました。夜明け前から待つご来光はいつもと気持ちの持ち方が違うのか新鮮にかつ神秘的に感じました。
新しい年の幕開け、ご来光を浴びながら心機一転、気持ち新たに出発という「けじめ」として、今年も初日の出を拝み祈ることができました。
地元若者の初日の出スポットとして注目を浴びている「ふれあいビーチ」(通称「ハワイ」と呼ばれています。)。芝生広場からハートのリングに初日の出を収めました。
熊野市から紀宝町まで約22キロ砂利浜が続いている七里御浜は、平安時代後期以降、熊野三山への参詣道として、「蟻の熊野詣」と言われるくらい多くの人に利用されてきました。そして、今でも熊野三山へと向かって歩く人の姿を見かけることがあります。
いつも見慣れた、当たり前の光景となっているこの場所ですが、ほんとにええとこやなぁ~と思いながら、幼いころからの遊び場だった砂利浜で懐かしく小石で顔を作ってみました。いろいろな表情ができ、自画自賛しながら、この雄大な山・川・海の大自然がギュッとつまっている中に生まれ育ったことを誇りに思い、"もっと、もっと多くの方にこの素晴らしさを伝えていこう!"と誓った初日の出でした。
大自然を満喫しに「よしくま」へ遊びにお越しください!
2018年12月13日「よしくまアドベンチャーin志原 ジオの宝探し」を開催しました。
吉野熊野国立公園 田辺 中村千佳子
皆さん、こんにちは。田辺自然保護官事務所アクティブ・レンジャーの中村です。はやいもので今年も残すところあとわずかとなりました。振り返ってみると沢山の出会いと、周りの皆さんに助けていただいた1年でした。残りの日々も大切に元気よく過ごしたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。
さて、12月1日(日)に平成30年度吉野熊野国立公園子どもパークレンジャー事業の最終回となる「よしくまアドベンチャーin志原 ジオの宝探し」を開催しましたので、このことについて報告します。
今回のアドベンチャーは、白浜町志原海岸にて、砂岩と泥岩が交互に積み重なってできたサンドイッチ状の地層や海食洞などの海からの浸食作用によってできたダイナミックな地形などを観察しながら、大地の成り立ちに由来する自然の宝物について楽しく学ぶ事を目的として開催しました。当日は15名の元気な子どもたちが参加しました。
  |
|
| 日本の奇岩百景のひとつベアーズロック 志原海岸にある海食洞 |
志原海岸は国道42号沿いにあることから多くの人が訪れる場所です。しかし、海食洞があることは広く知られておらず、参加者も海食洞には行ったことがない子ばかりでした。
磯を観察しながら歩いていると、参加者からは「この模様はなに?」「この実はなんていう名前?」「なぜこんな形なの?」など沢山の質問が飛び交い、講師の説明に熱心に聞き入る姿が印象的でした。
海食洞に到着すると、「おー!すごい!」「でっかい!」と驚いた声が聞こえてきました。波の浸食をうけこのような形になったと教えてもらい、近くでは昔いきものが住んでいた痕跡が化石になった「生痕化石」を観察しました。それから自然の宝物探しゲームをして、それぞれの宝物を集めました。中には貝の化石を見つけた子もいました。
  |
|
| 講師の話を熱心に聞く参加者 貝の化石 |
最後に、今日見つけた宝物を石に描きました。磯の生き物や木の実、海食洞だけでなく「よしくま、ありがとう」「またくるね!」とメッセージを書いてくれた子もいて、吉野熊野国立公園を大切に思い、自然に感謝してくれている事にスタッフ一同感激しました。
これからも、身近な自然に目を向けふるさとを大切にする気持ちを育んでいく活動を応援していきたいと思っています。
  |
|
| ストーンペイント 集合写真 |
2018年12月11日Memories of Oodaigahara in 2018
吉野熊野国立公園 小川 遥
皆さま、こんにちは。吉野の小川です。
12月に入り、2018年もあとわずかとなりました。寒さも増してきたので、近頃はこたつでみかんに幸せを感じる日々を過ごしております。
さて、大台ヶ原も冬に入り、12月3日15時に山頂へ繋がる大台ヶ原公園川上線(通称:大台ヶ原ドライブウェイ)が閉鎖されました。今シーズンもたくさんの方が訪れ、景色や生きものを楽しんでいただけたことと思います。そこで今回は、大台ヶ原で活動するパークボランティア(PV)の活動とともに、2018年に大台ヶ原が私たちに見せてくれた景色の数々を振り返っていきたいと思います!
まずは春。
4月20日に開山してすぐの頃はまだ冬の様相を残しています。やがて、鳥が囀り、色とりどりの花が咲き、瑞々しい新緑へ移り変わる様子を楽しむことができます。パークボランティアも早速活動を開始し、利用者の方が分かりやすく、気持ちよく楽しめるよう願いながら、冬の間に汚れた看板拭きや歩道の確認、ごみ拾いを行いました。
 |
 |
 |
| PV活動(看板拭き) | ツツジの開花 | 新緑と熊野の海 |
次に夏。
1年を通して降雨が多い大台ヶ原ですが、梅雨から夏にかけて見ることができる、しっとりした雨上がりの森はおすすめです。鮮やかな新緑と水が滴る深い緑の苔がむす世界のなか、時には霧が出て幻想的な雰囲気が漂う西大台を味わった方も多いのではないでしょうか。
本格的な夏になると大台ヶ原でも暑い日がありましたが、パークボランティアの自然観察会にもたくさんの方に参加いただきました。正木峠付近では、一足早くシロヤシオが色づいていく様子を見ることもできました。
 |
 |
 |
| 雨上がり新緑の西大台 | PV自然観察会 | シロヤシオの色づきと日出ヶ岳 |
そして秋。
夏から秋にかけて例年以上に台風の影響が強い季節でもありましたが、晩秋は秋晴れとなる日も続き、紅葉を楽しむことができました。パークボランティアもボランティア内での学習会を開催し、今後の観察会をより良いものにすべく、実践練習をしながら自然情報を収集しました。
|
|
 |
 |
 |
| シロヤシオの紅葉 | ナナカマドの紅葉 | PV学習会 | 大蛇嵓の紅葉 |
最後に冬。
冬期閉鎖があるため冬を楽しめる時期は短くなりますが、日によっては樹氷や冠雪を見ることができます。更にこの時期は最も空気が澄み渡り、木々の葉も落ちているため、遠方を望むことができます。パークボランティアも11月下旬には、この1年の感謝を込めた清掃活動と自然再生(※)へ向けた作業を行い、大台ヶ原での今年度の活動を締めくくりました。
 |
 |
 |
 |
| 樹氷(ドライブウェイ) | 樹氷 | 山頂から望む大峰山系 | PV活動(自然再生事業) |
皆さんに是非見ていただきたい大台ヶ原の姿はまだまだあります。そして2019年の大台ヶ原は、また違った姿を見せてくれることでしょう。今年行かれた方もまだ行ったことがない方も、来シーズンの大台ヶ原に思いをはせつつ、次の開山を楽しみにお待ちください。そして、冬の間もAR日記を通し、大台ヶ原の様々な話をお届けしたいと思っています。そちらもどうぞお楽しみに!
それでは皆さま、素敵な新年をお迎えください。
-------------【大台ヶ原公園川上線(大台ヶ原ドライブウェイ)冬期通行止め】------------
平成30年12月3日(月)午後3時~平成31年4月19日(金)午後3時(予定)
上期間中は冬期閉鎖のため、大台ヶ原山上へ通じるドライブウェイは通行止めです。
詳細はこちら→ http://www.pref.nara.jp/secure/205319/toukituukoudome.pdf
※ 環境省では、森林生態系の衰退を食い止め、大台ヶ原の自然を後世に残すために「大台ヶ原自然再生事業」を行っています。シカの侵入を防ぎ、植生の回復を促す防鹿柵(ぼうろくさく)の設置、シカによる樹木の皮剥を防ぐためのネット巻など様々な取組み(詳細はこちら→ http://kinki.env.go.jp/blog/2018/07/post-83.html)や普及啓発活動を実施しています。パークボランティアもその補助となる作業を随時行っています。
2018年11月06日「よしくまアドベンチャーin神島へシーカヤックで渡ろう!」を開催しました。
吉野熊野国立公園 田辺 中村千佳子
田辺自然保護官事務所アクティブ・レンジャーの中村です。爽やかな風が吹き、紅葉の便りが届く季節となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
この季節、私の楽しみは山のてっぺんで、地元で採れたみかんを食べながらよしくまの景色を眺めることです。
 |
|
| 田辺市高尾山山頂より |
さて、10/21(日)に田辺市神島にて平成30年度吉野熊野国立公園子どもパークレンジャー事業「よしくまアドベンチャーin神島へシーカヤックで渡ろう!」を開催しましたのでご報告します。
今回のアドベンチャーは、地域の子ども達に、普段は上陸することのできない神島にシーカヤックで渡る体験をすることで、神島の自然や文化について学び、地域の豊かな自然やその恵みに目を向けるとともに、海岸の漂着ゴミを回収しながら、海が抱える環境問題に触れ、考えるきっかけとして目的として開催しました。当日は近隣の市町から40組を超える応募があり、その中から抽選で選ばれた10組20名の親子が参加しました。
まずは、今回のアドベンチャーの目的やシーカヤックの説明を聞いた後、実際にシーカヤックへ乗り込み、パドルで漕ぐ練習をしました。
シーカヤックの説明 神島
それから、神島へ向け出発しました。風が少しあるものの、波もなく天気に恵まれ、参加者は気持ちよさそうにシーカヤックを漕いでいました。はじめはパドルの漕ぐリズムが全く合わず真っ直ぐに進めなかった人たちも、次第に息が合いとても速く進んでいました。
  |
|
| 石碑の見学 磯の見学 |
  |
|
| 回収したゴミ 集合写真 |
神島に上陸後、講師から観察時の注意事項を聞いた後、浜辺の植物や磯の生き物などを観察しました。
タイドプールには小さな魚やカニなどがいて、子どもたちは熱心に生きものについての説明を聞いていました。また、砂浜には動物の足跡がありタヌキやアライグマであると学びました。
浜辺に生えているハカマカズラの葉は、台風による塩害で葉が変色し枯れているのが多かったのですが、参加者は興味深げに神島のハカマカズラを観察していました。
その後、みんなで漂着ゴミを回収しました。回収中には、大きなロープや網などが見つかりました。回収したゴミの量は80キロで、ゴミはみんなでシーカヤックに乗せて港まで戻りました。
これらの経験をとおして、参加者からは「神島の磯を探検できて楽しかった!」「動物が泳いで海を渡ることに驚いた。餌になるような物を捨ててはいけないと思った。」「海から見る田辺市は綺麗だった。」「シーカヤックを漕ぐのが難しかったけど、普段行けない神島に行けて嬉しかった。」などの感想が寄せられました。
これからも、地域の子ども達が色々な体験をしながら、豊かな自然にふれあう機会を作っていきたいと思います。
注:神島は、田辺市により上陸が禁止されています。今回は特別に市の許可を得て上陸しました。また、神島は吉野熊野国立公園第1種特別地域及び国の天然記念物に指定されています。
2018年09月30日大台ヶ原の秋の訪れ
吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥
皆さま、こんにちは。吉野自然保護官事務所の小川です。
涼しい風が吹き、日が暮れる頃には鈴虫の鳴き声が聞こえ、町中でもだいぶ秋らしさを感じる頃となりました。1年を通して旬の味覚を味わいたい私にとって、特に食指が動く季節でもあります。さんま、きのこ、栗、さつまいもなど魅力的な味覚がたくさん並ぶなか、いかに効率よくどれも逃さず、美味しく食べていくかを考えるだけで楽しい日々です。
さて、山の秋は麓よりも少し早くやってきております。大台ヶ原ドライブウェイ沿いにはススキの穂が茂り、山中でも紅葉し始めた木々が少しずつ見られるようになりました。(※例年大台ヶ原の紅葉は10月中旬頃からになりますが、色づき具合はその時の天候によって差があります)
本格的な紅葉はこれからになりますが、徐々に秋の色が深まっていく、この時期ならではの山の風景を楽しむことができます。
なお、大台ヶ原は平地より10度程気温が低く(天候等により変動あり)、これから更に寒さが増していきます。雨具や防寒具などの備えを確認の上、お越し下さい。
|
|
|
|
ススキ群生(大台ヶ原ドライブウェイ沿い) |
シロヤシオの色づき(正木峠付近から日出ヶ岳) |
また、吉野自然保護官事務所では、旬の大台ヶ原をより堪能していただける自然観察会を予定しております。大台ヶ原で活動するパークボランティアから、東大台にまつわる話を深く知ることができる、今シーズン最後の機会となります。皆さま、是非ご参加ください。大台ヶ原で待っております☆
☆吉野熊野国立公園 大台ヶ原地区自然観察会☆
日程: 10月7日(日)
詳しくはHP(http://kinki.env.go.jp/to_2018/post_123.html)をご覧下さい♪
2018年09月07日この日何の日
吉野熊野国立公園 青谷 克哉
Q「なぜ、あなたはエベレストに登りたいのですか?」
A「そこにエベレストがあるから。」
登山家のジョージ・マロリー氏が言ったとされる有名な台詞です。日本では「そこに山があるから。」で知られていると思います。山に登るのも良いですが、遠くから眺める方が好きな吉野自然保護官事務所の青谷でございます。
さて、既に過ぎてしまったのですが、8月11日は国民の祝日「山の日」でした。平成28年から新たに祝日として加わった「山の日」。海の日の親戚のように聞こえる「山の日」とは、そもそもなんぞや?という人もいるのではと思い、僭越ながら今回は「山の日」について少しだけ紹介をさせていただきます。
山の日とは、国民の祝日に関する法律によりますと、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」とあります。吉野自然保護官事務所管内には大台ヶ原や大峰山系、近畿地方環境事務所管内まで広げれば那智山や六甲山などが加わり、国立公園外を見渡せば、ご近所には金剛山、葛城山など山は身近に沢山存在しています。それもそのはずで、日本は国土の7割ほどが山地となっているのです。半分以上が山!これは、山と関わらないというのは不可能です。
古来より、人は山から様々な恵をいただいてきました。薪や建材など木材としての木、キノコや山菜、獣肉などの食料。また、水源地は山に多く、その水は川になり田畑と私達の喉を潤します。登山などのアクティビティを楽しめる場としての利用もあります。
他にも、信仰や修行の場にもなったり、神様の逸話や妖怪話などなど、人は山や自然に対し畏敬、畏怖の念を持ってきました。
山中の森林や頂上からの眺めは神秘的であり、荘厳な雰囲気を醸し出しているものもあるので、そのような念を抱くことに疑問はありません。私がこの地に着任以来1番素晴らしいと感じた風景は、山上ヶ岳から見た日の出でした。
山上ヶ岳宿坊近くからの風景(大峰山)
やはり、山からの日の出は登ってみて実際に見ていただきたいです。
このように、我々は海と同じく山とも切っても切れない縁で繋がっていると言えるでしょう。来年の「山の日」には、そんな山に対して少しでも思いを馳せていただければと思います。
2018年08月15日『上北山村 神秘の森 荘厳の山 大台ヶ原を歩く』
吉野熊野国立公園 小川 遥
皆さま、こんにちは。吉野自然保護官事務所の小川です。
8月に入り立秋も過ぎましたが、暑い日が続きつつも朝夕には涼しい風を感じる日も出てきました。
とはいえ、暑さにはまだまだ注意が必要です。私も、スイカにトマト、ナスなどさっぱりした旬の野菜を楽しみながらも、体力をつけるべくお肉は欠かさず食べている日々を送っています。
さて、本日は、8月1日に開催した大台ヶ原ガイドウォーク『大台ヶ原を歩く』の様子をお届けします!(※7月28日開催分は、台風12号による影響が予想されたため、中止となりました)
このガイドウォークには、大台ヶ原を周回する歩道を歩く「西大台ツアー」と「東大台ツアー」のほか、大台ヶ原自然再生事業の取り組みにふれる「自然再生ツアー」があります。
「自然再生ツアー」では大台ヶ原自然再生推進委員会の委員でもある奈良教育大学 松井淳教授の案内により、東大台の自然再生推進事業の実施場所をめぐって、大台ヶ原の現状を見聞きしました。普段は入ることができない防鹿柵(ぼうろくさく)内にも入り、幼木の育ち具合など柵の中と外の違いを見ていただきました。
現在、大台ヶ原で目にする景色は、数十年前から変わらない場所もあれば、大きく変わってしまった場所もあります。何が変わったのか、どうして変わってしまったのか、なぜ自然再生の取組みが必要なのか。このツアーで、豊かな自然の中でも随所で見られるシカによる森林への影響の様子など、何気なく歩くだけでは気が付かない部分を知っていただけたのではないでしょうか。
「西大台ツアー」と「東大台ツアー」では、昨年10月より登録が始まった大台ヶ原登録ガイド(詳しくはこちら→http://vill.kamikitayama.nara.jp/guide/)の案内のもと、原生的な雰囲気あふれる西大台と雄大な景色が味わえる東大台をそれぞれ堪能していただきました。
吉野熊野国立公園大台ヶ原を知っていただくために企画したガイドウォーク『大台ヶ原を歩く』も残すは9月開催のみとなりました。この機会を逃さず、是非参加してください。皆さまをお待ちしております☆
☆上北山村 神秘の森 荘厳の山 「大台ヶ原を歩く」☆
日程:9月28日(金)
内容:大台ヶ原登録ガイドや自然再生に詳しい特別講師による、ひと味違う大台ヶ原を楽しめるガイドウォークです(西大台、東大台、自然再生の3ツアーから選択)。
※公共交通機関の使用による参加が必須です。
※好評につき、西大台ツアーは満員となりました。
詳しくはこちら→ http://vill.kamikitayama.nara.jp/
2018年08月03日「よしくまアドベンチャーinウミガメ調査隊になろう!」を開催しました
吉野熊野国立公園 中村千佳子
みなさん、こんにちは。田辺自然保護官事務所アクティブ・レンジャーの中村です。毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、7月7日(土)・13日(金)・16日(月・祝)にみなべ町で子どもパークレンジャー事業「よしくまアドベンチャーinウミガメ調査隊になろう!」を開催しましたので、ご報告します。
今回のアドベンチャーは、地域の子どもたちにアカウミガメの産卵観察や調査体験を通じて、自然に対する興味を持ってもらい、改めて地域の自然に目を向けるきっかけになることを目的として開催しました。当日は12名の子どもたちが参加してくれました。
座学の様子
第1回目は、吉野熊野国立公園の千里の浜に上陸・産卵するアカウミガメの生態と関係者による保護活動・調査について学びました。子どもたちは、熱心にメモをとりながら話を聞き、手を挙げて質問をしていました。
第2回目は、実際に浜に出てアカウミガメの産卵の観察と調査・保護活動の体験をしました。産卵の観察は母ガメの邪魔にならないよう、産卵がはじまるまで物音を立てずに静かに待たなくてはいけません。
この「待つ」ということが子どもたちにとって一番の試練でした。なぜなら、母ガメは穴を掘り始めたとおもったら止めて、別の場所へ移動してまた穴を掘る、という行動を繰り返すので、長時間待たなければならなかったからです。最終的には子どもたちの目の前で産卵がはじまりました。体験終了後、子どもたちは興奮した様子で「すぐ目の前にカメがきたよ!」と教えてくれました。
母ガメになった気持ちで穴を掘ろう 産卵の様子
第3回目は、第2回目で観察した母ガメが今シーズン3回目の産卵であったことや、2年前にも千里の浜に上陸していたことについて学びました。
その後、母ガメの気持ちになって昼間に上陸しない理由を知るために穴掘り体験をしました。子どもたちは一列に並んで母ガメのように手足を使って穴を掘りますが、砂が熱くてなかなか深く掘れませんでした。講師がお手本に穴を早く深く掘ったのを見て子ども達は驚くとともに悔しそうでした。
そして、みんなで掘った穴で砂の表面と下の方の温度を調べました。表面はとても熱いのに、下の方は冷んやりとしていていました。
講師から、昼間は砂浜が熱すぎて産卵に上陸しないことや子ガメの性別は砂の温度で決まることを学びました。
集合写真
子どもたちからは「浜を歩いたとき、砂に足が埋まって歩きにくく、産卵のパトロールをしている人は大変だなと思った。」「毎晩、パトロールする人は凄いなと思った。昼の砂浜はとても暑いけど穴を掘ると中は冷たかった」「みなべ町に住んでいるがウミガメの産卵を見たのは初めてだった。必死に産んでいる感じがして感動した。」「どんなふうに穴を掘って卵を産むのかよくわかった。自分で海に行ったときにも探せたらいいなと思った」などの感想が寄せられました。
これらの経験を通して、子どもたちには自然の中で遊ぶだけでなく、一歩踏み出して考える事でアカウミガメの調査や保護活動に関心を持ち、自然を守り残していく気持ちにつながってくれるといいなと思いました。
次回のよしくまアドベンチャーもお楽しみに!
2018年07月31日「よしくま」の自然情報
吉野熊野国立公園 岩田佐知代
こんにちは 熊野自然保護官事務所アクティブ・レンジャーの岩田です。
植物の名前には、その植物を発見した人名、発見された地名、生育場所の特徴、形態など様々な由来があります。
今回は、名前に「ハマ」がつく植物をご紹介いたします。
太平洋に面した吉野熊野国立公園には、海岸沿いに「ハマ」のつく名前の海岸植物がたくさん生育しています。
「ハマ」がつく植物は、海岸沿いに多く生育し、波や潮風などの影響を受けても耐えて丈夫に育つことができる植物たちにつけられた名前です。実際に触ってみると、塩分や乾燥に耐えられるように葉に厚みや毛があったり、強い潮風に耐えられるように葉が少し小さかったり、草丈が低かったりして、それぞれがその場の環境に適応できるような形態になっているということがわかります。
和歌山県新宮市三輪崎(みわさき)にある孔島・鈴島(くしま・すずしま)では、多種多様な生物の中にハマヒルガオ、ハマウド、ハマアザミ、ハマナタマメ、ハマボウ、ハマゴウ、ハマエンドウ、ハマオモト、ハマヒサカキ、ハマダイコン、ハマナデシコ、ハマカンゾウ、ハマボッス、ハマナツメ、ハマエノコロなど名前に「ハマ」のつく多くの植物が生育し、花や実などを四季それぞれに観察することができます。
みなさんは写真の「ハマ」のつく名前の植物を観察されたことありますか。
紹介した植物のほかにもまだまだ名前に「ハマ」のつく植物はありますが、身近なところで観察できる「ハマ」のつく植物を探してみてください。
孔島・鈴島は、野鳥の絶滅危惧種であるウチヤマセンニュウの繁殖場所としても知られ、野鳥や植物の観察会も開催されています。また、地域の方々の散策、憩いの場としても利用されていて、すばらしい自然環境を保全するために地域で清掃活動が毎年行なわれています。
みなさんも「よしくま」にお越しの際には、磯の香り漂うこの孔島・鈴島にぜひ、お立ち寄りください。
孔島・鈴島 (野鳥&植物観察会の様子)
孔島・鈴島の海岸 (南紀熊野ジオパーク・ジオサイト)
孔島の海岸造形 鈴島の奇石



























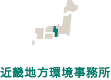
皆さま、こんにちは。吉野の小川です。
遂に2019年となりました。1月も半ばを過ぎたものの、残念ながら正月にお餅を食べることができなかったので、この先もまだまだお雑煮や焼き餅、ぜんざいなどを食べていこうと、私の中で密かな餅ブームが到来しています。
ところで2019年といえば、干支はイノシシにも象徴される己亥、恵方は東北東です。そこで今回は、今年の大台ヶ原をより楽しんでいただくために、2019年大台ヶ原の恵方を紹介します!
地図とコンパスを取り出し、大台ヶ原における大体の東北東方面を確認してみると・・・。そこには、大台ヶ原の山頂である日出ヶ岳(ひでがたけ)があります。
日出ヶ岳(標高約1,695m)にはベンチや地図が備わる展望台があり、昼食やコース確認を兼ねたちょっとした休憩にオススメです。山中で唯一避雷針が備わっている場所でもあるため、天候が急変しやすい大台ヶ原ではチェックしておくべき場所の一つです。春から夏には周辺でシャクナゲが咲き、耳を澄ませると遠くの山で鳴く鳥の声が聞こえ、夏から秋にはアキアカネが飛び交います。木々が芽を出し、美しい新緑から紅葉、そして冬の樹氷へと移り変わる山の四季を感じることができます。
展望台から恵方を含む東の方角を見ると、熊野の海を見渡すことができ、空が澄んだ日には、日の出とともになんと富士山を拝めることがあります。更にこの方角は、日本三大渓谷に数えられる大杉谷と繋がっており、そちらには大きな滝やそそり立つ岩壁が連続し、見事な景観が広がっています。
(※大杉谷は中上級者向け登山道であり、安全面上、大台町にある大杉峡谷登山口から大台ヶ原へ登るコースを推奨しています。ヘルメット着用を含む装備の準備、ルートや天候などの事前確認、山小屋への宿泊、登山届の提出など十分な計画を立ててお越し下さい)
また、日出ヶ岳展望台から西の方角に目を向けると、近畿最高峰の八経ヶ岳を含む、世界遺産の一部である大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)が通る大峰山系を一望できます。北の方角には高見山地や御在所山方面に連なる山々、南の方角には大台ヶ原の正木峠に続く景色が広がります。
現在は車道が冬期通行止めとなっていますが、今年は大台ヶ原に行こうと思っている方もまだ予定にはない方も、節分の日には、大台ヶ原の恵方に思いを馳せてみてください。展望台でのんびりしてから東大台を一周するのもよし、大杉谷から日出ヶ岳まで登ってくるのもよし、早朝から日の出と富士山を眺めるのもこれまたよし!是非大台ヶ原にお越しいただき、2019年にしか味わえない日出ヶ岳をお楽しみ下さい。今年もたくさんの方々に、大台ヶ原を気持ち良く楽しんでいただけることを願っております。
----------------------【大台ヶ原公園川上線(大台ヶ原ドライブウェイ)冬期通行止め】---------------------
平成30年12月3日(月)午後3時~平成31年4月19日(金)午後3時(予定)
上期間中は冬期閉鎖のため、大台ヶ原山上へ通じるドライブウェイは通行止めです。
詳細はこちら→ 【報道資料】平成30年度 奈良県内 冬季通行止について(リンク)